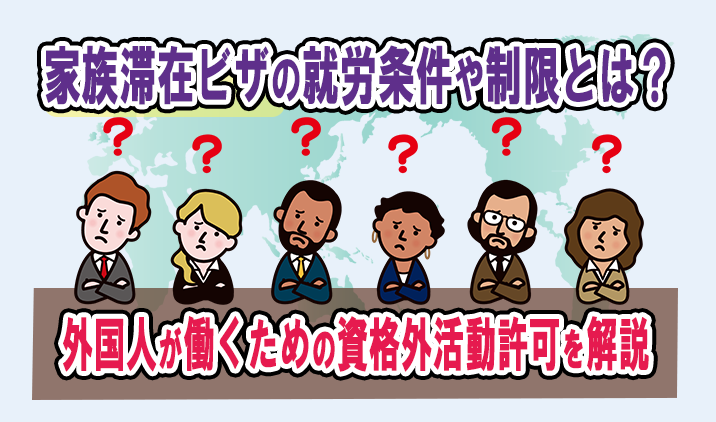2024/5/1

外国人雇用
外国人を雇用・採用するには?手続きと雇用可能な在留資格、注意点を解説
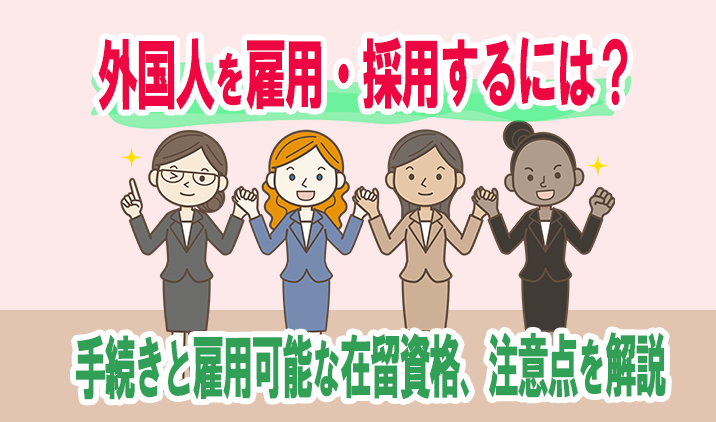
外国人雇用には独自の制度や手続きが存在し、不安を感じる声も多く聞かれます。本記事では、そうした懸念をあらかじめ払拭しておくための外国人を雇用する際の手続きや注意点について、詳しく解説しています。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
| ✓ 日本における外国人雇用は、近年顕著な増加傾向にあり、特に30人未満の企業におけるニーズが高い
✓ 行政は外国人労働者の人権侵害問題や、外国人による犯罪の増加に対応すべく、平成16年(2004年)に不法就労者の取り締まりや罰則を強化した ✓ 外国人雇用にあたっては、「職種に適した在留資格を有している人材」を採用しなければ罰則を受けてしまう ✓ 在留資格は、就労に制限がない4種類の身分系と、就労内容に制限がある19種類の在留資格がある ✓ 就労資格を得ていたとしても、単純作業の業務に従事することは許可されていない ✓ 留学生などのアルバイトは「資格外活動許可」を取得する必要があり、労働時間における制約に注意が必要である ✓ 外国人を採用するにあたっては、在留許可の内容を綿密に調査し、業務に合致する在留資格かどうかの確認作業が必要である ✓ 入国管理局による就労ビザの審査は、通常1〜3か月ほどかかる ✓ 雇用する前に労働条件を明示し、同意を得ることが必要である ✓ 採用後は、ハローワークに外国人雇用状況の届出をしなければならない ✓ 同一労働同一賃金の原則と最低賃金法の遵守は当然のこととして、コミュニケーションを保ち続けるための職場環境構築が重要である |
外国人雇用は、日本の少子高齢化による人材確保を解消するカギとしてますます注目されています。外国人材の多様な視点とスキルは企業の競争力を高め、新たなイノベーションを生み出す可能性も秘めています。しかし一方で、外国人雇用には独自の制度や手続きが存在し、不安を感じる声が多く聞かれるのも確かです。
本記事では、そうした懸念をあらかじめ払拭しておくための外国人を雇用する際の手続きや注意点について解説します。あらかじめ概要を把握することにより、スムーズな雇用環境を整えていきましょう。
1.外国人雇用の動向
日本における外国人雇用は、近年顕著な増加傾向にあります。多様な背景を持つ外国人労働者が市場に参入することで、国内企業の国際競争力強化に寄与しています。
一方で、言語の壁や文化の違いが課題となりつつあり、企業と外国人労働者双方が理解を深めながら、新たな環境醸成について模索していくことが今後の課題です。ここでは、外国人労働者数の推移と雇用に関する課題について解説します。
1-1.外国人労働者数の推移
外国人労働者の数は、前年比で12.4%増の2,048,675人であり、届出が義務化された平成19年(2007年)以降の最高記録です。国籍別ではベトナムが最多で、外国人労働者数全体の25.3%を占めています。次いで中国(19.4%)、フィリピン(11.1%)と続きます。在留資格別では「専門的・技術的分野」が24.2%増、「技能実習」が20.2%増で対前年の増加率が顕著です。
外国人を雇用する事業所は前年に比べ6.7%増の318,775所で、これも平成19年(2007年)以降の過去最高を更新しました。特に「30人未満」規模の事業所の割合が最も多く、事業所全体の61.9%(外国人労働者数全体では36.1%)を占めています。
産業別では「製造業」が外国人労働者数の27.0%を雇用しており、事業所数では「卸売業、小売業」での雇用が最も多く、全体の18.7%を占めています。これらのデータからも、外国人労働者雇用の増加傾向が明らかです。

※「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)より引用し加工
参考:「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和5年10月末時点)
1-2.外国人労働者の雇用に関する課題
外国人の単純労働者は、安価な労働力として賃金を安く抑えたい企業や、日本人があまり就きたくない職種により労働力不足が深刻化している企業にとって、欠かせない存在となっています。その一方で、不法就労により劣悪な労働環境に甘んじている外国人労働者が多く存在するのも事実です。
その問題に対処するため、行政は外国人労働者の人権侵害問題や、外国人による犯罪の増加に対応すべく平成16年(2004年)12月に入管法の一部を改正し、不法就労者の取り締まりや罰則を強化しました。
また実際の雇用現場では、言語やビジネス習慣の違いなどから、トラブルを生じやすいのも事実です。したがって外国人を雇う際には、入管法をはじめとした雇用の手続きを十分に把握し、慣習やビジネス習慣の違いについて理解していくことが重要です。
2.雇用・採用できる外国人の在留資格
日本での外国人雇用には、「職種に適した在留資格を有している人材」を採用しなければなりません。在留資格には、就労が許可されているものと、そうでないものがあります。
在留資格は、就労に制限がない4種類の身分系と、就労内容に制限がある19種類の在留資格があります。なかでも雇用や採用に関係する在留資格をピックアップし、下表にまとめました。
| 雇用・採用に関係する在留資格の種類 | 雇用・採用に関係する主な在留資格 |
| 日本での地位や身分に基づく在留資格 | 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」 |
| 就労目的の主な在留資格 | 「教授」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「技能」「特定技能」など |
| 非就労の主な在留資格 | 「留学」「家族滞在」「特定活動」など |
「留学」「家族滞在」「特定活動」などの就労資格がない場合でも「資格外活動許可」を取得することで、週28時間までのアルバイトが可能です。ただし、資格外活動許可は、既存の在留資格の活動を妨げない範囲でのみ付与されます。
また、在留資格がない状態での日本在留や在留期限が過ぎている場合は、不法滞在となります。さらに、虚偽や不正で入国許可を得た場合や在留資格に基づく活動を一定期間行わずに在留している場合などでも、在留資格取消しの可能性もあるため注意が必要です。
ここでは、それぞれの種類に分けて解説します。
2-1.日本での地位や身分に基づく在留資格
「身分又は地位に基づく在留資格」は以下の4種類があり、活動に制限はありません。
| 地位や身分に基づく 在留資格 |
該当者 |
| 永住者 |
|
| 日本人の配偶者等 |
|
| 永住者の配偶者等 |
|
| 定住者 |
|
基本的にどのような職種にも就けるため、雇用側にとっては貴重な存在です。
2-2.就労ビザ(就労が認められている在留資格)
就労できる在留資格は、以下の19種類です。
|
就労できる19種類の在留資格(就労ビザ) |
|||
| 外交 | 公用 | 教授 | 芸術 |
| 宗教 | 報道 | 高度専門職 | 経営・管理 |
| 法律・会計業務 | 医療 | 研究 | 教育 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | 介護 | |
| 興行 | 技能 | 特定技能 | 技能実習 |
在留カードに記載されている「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と明記されています。
つまり「法律・会計業務」で在留許可を取得した外国人が、製造工場での製品のパッケージングや配送など、単純作業の業務に従事することは許可されていないことを意味します。
そのような業務に従事している場合、「資格外活動」を行っているとみなされ、違法労働となるため注意が必要です。
2-3.アルバイトの場合は資格外活動許可の申請が必要
例えば日本の大学に通う留学生は「留学」の在留資格であるため、アルバイトは認められていません。したがって、アルバイトで働きたい場合には「資格外活動許可」を取得する必要があります。ただし、現在の在留資格に関係する活動が妨げられてしまうものや風俗営業などの場合には、資格外活動許可は認められません。さらに、1週間あたり28時間以内という時間制限があります。
ここでの資格外活動とは、在留資格の範囲を超えて報酬を得る活動や事業を指します。資格外活動許可は、「技術」「人文知識」「国際業務」などの就労活動に制約がある就労系の在留資格を有する外国人や、「留学」などの就労が許可されていない在留資格を持つ外国人が対象です。
資格外活動許可の種類は、「包括許可」と「個別許可」の2種類です。
包括許可
包括許可は、特定の勤務先や業務内容を指定せずに資格外活動を許可する制度です。例えば、留学生がアルバイトをする際にこの包括許可があれば、仕事先を変えても再度の資格外活動許可の申請は不要です。この包括許可は、「留学」「家族滞在」「特定活動」などの在留資格者に与えられます。
ただし、包括許可には週28時間以内という制限があります。留学生の学校における長期休暇期間には、週40時間・1日8時間まで認められますが、これを超えると違法労働となるため、アルバイトを行う際には労働時間に注意しなければなりません。
個別許可
個別許可は、具体的な就労先や業務内容を指定する形で資格外活動を許可する制度です。就労系の在留資格を有する外国人が、その在留資格の範囲外で副業を行う場合に必要です。例えば、教授の在留資格を持つ外国人が、民間企業で語学講師として働く場合(語学教師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動に該当)などが該当します。
ただし個別許可では、単純労働は許可されません。また、在留資格の活動に対して資格外活動の比率が大きいと判断された場合、許可されない可能性があります。具体的には「在留資格の活動時間の半分を超えるかどうか」が目安とされていますが、時間だけでなくさまざまな状況によって判断されます。
3.外国人を雇用する際の手続きの流れ
近年、人材不足解消や多様な価値観を取り入れる目的のため、外国人雇用を検討する企業が増えています。しかし、外国人雇用には、在留資格の取得や社会保険の手続きなど、日本人とは異なる手続きが必要です。
ここでは、外国人を雇用する際の流れを以下の5つのステップに分けて解説します。
- 在留資格の調査を行う
- 面接や書類審査などの選考を行う
- 雇用契約書を作成・必要に応じて就労ビザの申請を行う
- 就労ビザの審査を待つ
- 外国人雇用状況届出書を提出する
適切なプロセスを把握し計画的に進めることにより、スムーズな外国人雇用につなげていきましょう。
3-1.在留資格の調査を行う
応募者が日本国内在住である場合、まず在留カードが偽造でないことの確認と有効期限を確認します。在留期限切れや不適合な在留資格の外国人を雇用した場合、雇用主は法的な罰則を受けるリスク(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科)があるため、慎重に調査を行わなければなりません。
この在留カードが偽造ではなく、有効期限が期限内であれば、次に記載された在留資格の内容と外国人が従事予定の仕事が適合するかを確かめます。在留カードに「就労不可」と表示されていた場合であっても、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されているのであれば、その範囲内での雇用が可能です。
応募者が海外在住で日本に招へいするケースでは、採用予定の職種がどの在留資格に該当するのかを確認し、学歴や実務経験等の要件をクリアしているかどうかの調査を行います。
3-2.面接や書類審査などの選考を行う
応募者が集まると、次は選考プロセスです。日本人の採用と同様に書類審査や面接を通じて、募集要件や求める人物像に合致する候補者を選びます。
外国人応募者は、日本人とは異なる文化的背景を持ち、職種別採用が普通であるため職掌範囲についての明確な区分意識を持っています。審査にあたっては、自己アピールに積極的な応募者を過大評価せず、実際の能力や経験を慎重に評価することが適切な人材採用には不可欠です。
外国人の採用面接では、応募者の日本語能力の流暢さに惑わされ、業務適性があると誤判断することがあります。言語能力の高さが職務適性を保証するものではないため、応募者の経験を詳しく確認することが重要です。
3-3.雇用契約書を作成・必要に応じて就労ビザの申請を行う
内定後は雇用契約書の作成です。雇用契約書は、日本人と同様法律に従った内容で作成し、内定した外国人が理解できる言語で明確な労働条件を記載しなければなりません。
双方の合意と署名により雇用契約が成立した後は、就労ビザの申請手続きへと進みます。就労ビザの申請手続きは、「日本に在留している外国人が就労ビザを申請する場合」と「海外から新たに採用し日本に招へいする場合」により手続きが異なります。
日本に在留している外国人が就労ビザを申請する場合
例えば新卒の留学生を採用する際は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更するための申請が必要です。通常、卒業予定年の12月から申請が可能で、結果が出るまで1~3か月かかるため、4月入社を目指す場合は1月下旬までに申請を済ませる企業が多いです。
日本にいる外国人を中途採用する場合、新しい職種に適合した在留資格への変更申請が求められます。これには、内定者が新しい在留資格の要件を満たしていることが前提です。
同じ職種での中途採用の場合、通常ビザの再申請は不要ですが、ビザ更新時には新しい雇用先の情報を提出する必要があります。
海外から新たに採用し日本に招へいする場合
外国人を日本に招へいする際は、まず「在留資格認定証明書」の取得が必要です。この証明書は、日本の出入国在留管理官署が発行し、外国人の滞在目的が入管法の資格要件に適合していることを証明します。
在留資格認定証明書の取得には1~3か月かかり、交付日から3か月間有効です。海外にいる外国人は、自国の日本大使館や総領事館で在留資格認定証明書を提出し、ビザを取得します。
3-4.就労ビザの審査を待つ
入国管理局による就労ビザの審査は、通常1〜3か月ほどかかります。
審査が通らない事例も存在し「職務が単純な現場労働であること」「企業の実態がないこと」「外国人労働者への過重労働が懸念されること」「学歴が不足していること」などが主な要因と考えられます。
審査が不許可となった理由によっては、状況を改善し再申請が可能なケースもあるため、入国管理局に審査が通らなかった理由を尋ねましょう。
3-5.外国人雇用状況届出書を提出する
不法就労の助長を避けるために、外国人の雇用における労務管理は厳格に行わなければなりません。まず、雇用した外国人の在留カードを確認し、コピーして保管しましょう。そして在留期限の管理を行い、期限が近づいている外国人従業員に対しては在留カードの更新を促し、新しい在留カードの提出を求めます。
留学生等のアルバイトやパートの場合には、1週間の労働時間が28時間を超えないようにするための管理が必要です。
次に、ハローワークに外国人雇用状況の届出をしなければなりません。これは事業主の義務であり、正しく届け出ないと罰金が科せられるため注意しましょう。届出方法は、雇用する外国人が雇用保険の被保険者になるかどうかで異なります。
- 被保険者にならない場合:「外国人雇用状況届出書 第3号様式」を提出します。
- 雇用保険に加入し被保険者となる場合:「雇用保険の被保険者資格取得届」を提出し、雇用保険の手続きを済ませましょう。
4.外国人を雇用する際の注意点
外国人労働者の雇用は、企業の成長と多様性を促す一方で、法的な要件や文化的な違いに対応するための新たな課題も浮き彫りにしています。ここでは、外国人を雇用する際に考慮すべき7つの注意点をピックアップしました。
- 在留カードで在留資格は必ず確認する
- 在留資格と業務内容が一致しているかを確認する
- 労働条件の認識が一致しているか確認する
- 日本語でのコミュニケーション能力を確認する
- 入社後のフォロー体制を構築しておく
- 同一労働同一賃金・最低賃金の制度は必ず守る
- 採用・退職時に雇用対策法に基づいた届出を行う
以下、それぞれについて解説します。
4-1.在留カードで在留資格は必ず確認する
在留資格は、外国人が日本で特定の活動を行うために必要な資格です。必ず確認するようにしましょう。
在留資格には、就労可能な資格と就労不可の資格が存在します。また就労可能な在留資格でも、種類により許可されている業務範囲や在留期間が異なるため、注意を要します。
雇用予定の外国人が既に在留資格を持っているケースでは、従事する業務が在留資格で許可されている業務範囲内に該当するかを確認しましょう。
また、在留資格の取得が初めての外国人労働者を雇用する場合、その外国人の職歴や学歴が自社の業務に適する在留資格を取得できるかについて、事前に調査することも必要です。
4-2.在留資格と業務内容が一致しているかを確認する
就労ビザの対象は、特定の学歴(大学や専門学校の卒業など)や実務経験を持つ、専門職に従事する外国人です。よって、学歴や経験が不要な単純作業を行う外国人は、このビザの対象外です。つまり「単純労働」としての就労ビザは認められていません。
例えば、一定の学歴や実務経験を持つ外国人でも、単純労働を行った場合には不法就労となり、その雇用主も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。ここにいう単純労働には、「工場労働者」「ウェイトスタッフ」「調理補助」「マッサージ師」「美容師」「理容師」「コンビニエンスストアの店員」「清掃員」「ドライバー」「警備員」などが該当します。
就労ビザを申請する際の重要なポイントは、外国人の学歴・専攻・実務経験の有無と期間です。基本的に、大学や専門学校の卒業資格がなく、関連業務の実務経験もない外国人は、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザが許可される可能性はきわめて低くなります。そのため、外国人を正式に採用する前に、最終学歴や専攻、関連業務の実務経験などを確認することが重要です。
4-3.労働条件の認識が一致しているか確認する
労働条件、例えば給与・勤務時間・残業時間などは、雇用する前に明示し、同意を得ることが必要です。求人募集と実情の相違があると、労働基準法違反が発生してしまうため注意しなければなりません。
日本語の理解度が低い場合、労働条件を適切に把握するのは困難かもしれません。そのため、労働者が労働条件を理解しているかどうかを確認するための時間が必要です。可能であれば、外国人労働者の母国語で「労働条件通知書」を作成することが望まれます。
さらに、労働条件を確認する際には、社会保険への加入状況についての説明が必要です。外国人労働者でも、常用雇用に該当する場合や、非常勤でも常勤の4分の3以上働く場合は、社会保険への加入が必須です。社会保険への加入が必要なのに加入させていない場合、雇用主は罰則を受ける可能性があります。これらの点を考慮に入れ、労働者の採用と管理を行っていきましょう。
4-4.日本語でのコミュニケーション能力を確認する
仕事の遂行において、従業員間のコミュニケーションは重要です。コミュニケーションが不十分な場合、業務の進行が滞ってしまう懸念もあります。さらに、指示が適切に伝わらなければ、業務上の大きなトラブルを引き起こしかねません。
同じ言語を話す者同士でさえ、他者の指示を完全に理解することは難しい場合があります。特に、言語の理解力が不足している外国人労働者とのコミュニケーションでは、トラブルが生じるリスクが高まります。
将来的な問題を避けるために、外国人を採用する際には、求める言語能力があるかどうかを事前に確認することが重要です。この点を考慮に入れて、採用プロセスを進めていきましょう。
4-5.入社後のフォロー体制を構築しておく
外国人労働者の能力を向上させるためには、適切な教育環境の提供が重要です。業務マニュアルの提供だけでは、指示通りの実行が担保されません。
日本と他の国では、仕事の進め方や文化が異なるため、指導した内容をすぐに理解し実行するのは難しいかもしれません。教育担当者は積極的にコミュニケーションを取り、上司は定期的に面談を行うなど、異なる国籍の労働者が協力して業務を遂行できるように、細やかなサポートを提供することが大切です。
さらに、日本人と外国人では文化が異なるため、コミュニケーションや業務遂行に問題が生じることもあります。そうした際には、日本人・外国人双方が互いの文化や仕事の進め方に理解を示し、歩み寄る姿勢を保つことが重要です。
相互のコミュニケーションを円滑にするためには、日本人労働者と外国人労働者が互いに理解し認め合う場を設けることも必要です。そうした中で、日本のマナーや職場のルールへの理解を求め、外国人労働者も歩み寄りやすくなる環境を作りましょう。さらに、長期休暇の制定や宗教に配慮した設備の整備なども、働きやすい職場づくりには有効です。
4-6.同一労働同一賃金・最低賃金の制度は必ず守る
日本人と同じく外国人に対しても、同一労働同一賃金の原則と最低賃金法は遵守しなければなりません。外国人であるからといって、適切でない賃金を設定することは違法です。
これらの法律を遵守しない場合、違法行為となり、不足分の賃金を支払わなければなりません。さらに注意が必要な点として、給与水準が日本人より低い場合、在留資格の取得が難しくなることもあります。
外国人であることを理由に待遇を差別することは許されず、入管では企業内で同じ業務を行う日本人の給与水準も確認します。したがって、外国人の待遇が公平であることも重要な要素です。
4-7.採用・退職時に雇用対策法に基づいた届出を行う
外国人の採用や離職の際には、雇用対策法に従って適切な手続きを行わなければなりません。届出の対象となるのは、日本国籍を持たず、「外交」や「公用」以外の在留資格を持つ雇用者です。
特別永住者については、採用時や離職時の届出は不要です。届出には、労働者名・在留資格・在留期間などがあります。これらの情報を定められた書式に記載し、管轄のハローワークに提出しましょう。届出を怠った場合には、30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
5.まとめ
本記事では、外国人を雇用する際の手続きや注意点について解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。
| ✓ 日本における外国人雇用は、近年顕著な増加傾向にあり、特に30人未満の企業におけるニーズが高い
✓ 行政は外国人労働者の人権侵害問題や、外国人による犯罪の増加に対応すべく、平成16年(2004年)に不法就労者の取り締まりや罰則を強化した ✓ 外国人雇用にあたっては、「職種に適した在留資格を有している人材」を採用しなければ罰則を受けてしまう ✓ 在留資格は、就労に制限がない4種類の身分系と、就労内容に制限がある19種類の在留資格がある ✓ 就労資格を得ていたとしても、単純作業の業務に従事することは許可されていない ✓ 留学生などのアルバイトは「資格外活動許可」を取得する必要があり、労働時間における制約に注意が必要である ✓ 外国人を採用するにあたっては、在留許可の内容を綿密に調査し、業務に合致する在留資格かどうかの確認作業が必要である ✓ 入国管理局による就労ビザの審査は、通常1〜3か月ほどかかる ✓ 雇用する前に労働条件を明示し、同意を得ることが必要である ✓ 採用後は、ハローワークに外国人雇用状況の届出をしなければならない ✓ 同一労働同一賃金の原則と最低賃金法の遵守は当然のこととして、コミュニケーションを保ち続けるための職場環境構築が重要である |
あらかじめ概要を把握しておくことで、いざ外国人雇用を検討する際にスムーズな対応ができます。とはいっても、在留資格の変更許可申請を行う際、申請者が適格であると判断したとしても、許可の下りないケースが多いことは確かです。
在留資格の変更が不許可となると、外国人本人のみならず企業にとっても大きな損失です。そのため、申請を行う際には、行政書士などの専門家に依頼することも一つの考えとして押さえておきましょう。
また、外国人労働者の雇用を推し進めるためには、求職者の生活や職場の環境を整備するだけでなく、職場や社員の意識も高めていくことが重要です。
外国人労働者の数は今後も増加し、企業における彼らの受け入れは近い将来には一般的になると予想されます。外国人労働者の受け入れに関する要点を理解し、彼らを円滑に雇用し、安心して働けるサポート体制を構築していくことが重要です。
そうした取り組みの積み重ねにより、外国人労働者が働きやすい環境を提供し、より多くの労働者から選ばれる企業を目指し、競争力を高めていきましょう。
この記事の監修

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に居住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。