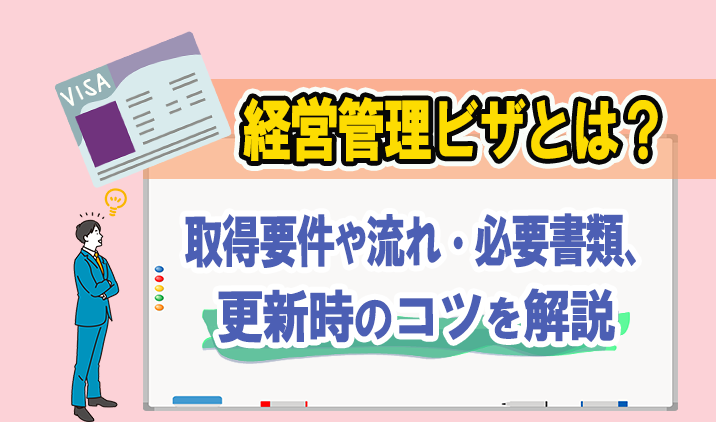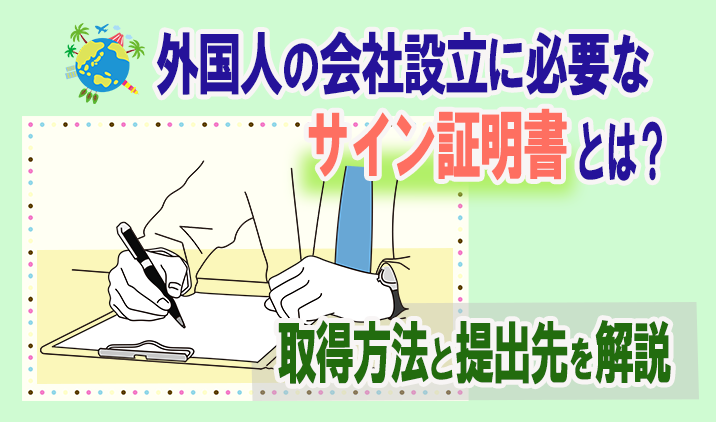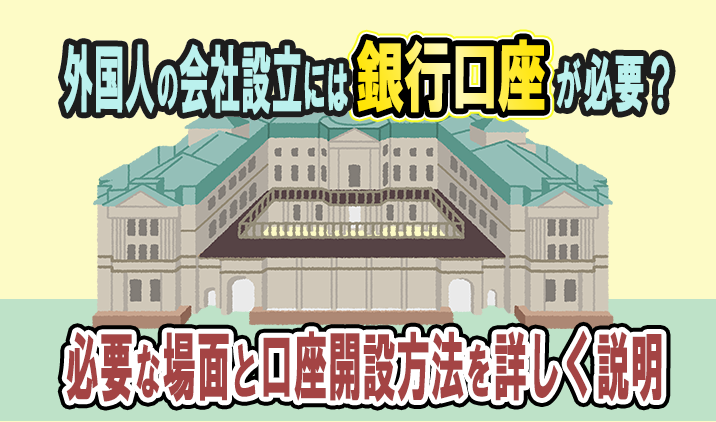2023/5/31

外国人の法人登記
外国人が日本で会社設立するには?条件、ビザなど手続きの流れを解説

外国人が日本で会社を設立するときは、日本に居住する日本人が会社を設立する場合と同様、会社設立登記(法人登記)が必要です。ただし、実際に日本に中長期滞在し、経営者として活動するには経営管理ビザの取得が求められます。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
| ✓ 外国人が日本で会社を設立し、日本で会社経営するときは、海外居住で経営する場合はビザがいらないが、日本に中長期滞在して会社経営するには経営管理ビザや永住権などが必要
✓ 日本でビジネスを始めるためには、会社設立と銀行口座が必要であり、それぞれの手続きで署名(サイン)証明書、印鑑証明書が必要となる ✓ 経営者として経営管理ビザ取得するには、①事業所が日本国内に確保されていること、②一定以上の事業規模(常勤職員2名以上又は資本金500万円以上)を満たすこと、③事業の適正性・安定性・継続性を示せること、④事業の経営に実際に従事することの4つの要件がある ✓ 日本で会社設立するには、先に会社設立登記をし、日本拠点で事業開始ができる状態となったあとに、経営管理ビザを申請するという手順が必要 |
本記事では、日本に会社を設立するための流れや注意点のほか、経営管理ビザの取得条件、会社設立登記に必要な書類について解説します。
正しい書類を準備して流れを知っておくことで、日本進出にあたっての会社設立と経営管理ビザ取得を滞りなく進めていくことができます。ぜひご覧になり、スムーズな会社設立を実現してください。
ビザ保証制度で当社がお手伝いした経営管理ビザ取得と会社設立を100%保証します
1.外国人が日本で会社設立して経営する条件とは?
日本国内、海外居住に関わらず外国人でも日本国内に会社を設立することは可能です。日本人が会社を設立するのと同様、公証人の認証を受けて定款を作成し、出資金を払い込み、会社設立登記を申請すれば、外国人も会社を設立することができます。
しかし、外国人が日本国内で経営者として中長期滞在し、ビジネス活動するためには、以下の条件を満たすことも求められます。
- 「経営管理」「永住者」や「日本人の配偶者等」などのビザ(在留資格)を持つこと
- 経営者になれるビザ(在留資格)がない場合には、資本金として500万円以上を準備できること
- 署名(サイン)証明書又は印鑑証明書を有すること
- 日本の銀行口座を持つこと
それぞれの条件について説明します。
1-1.経営管理、永住者や日本人の配偶者等などのビザ(在留資格)を持つこと
外国人は国内、海外在住に関わらず日本で会社を設立することができます。
しかし、日本国内に滞在し、経営者として活動するには会社経営ができるビザ(在留資格 ※以後、理解しやすいよう”ビザ”と表示ます。)が必要です。短期滞在ビザや家族滞在、留学ビザなどでは日本国内で報酬をもらいながら経営者として活動することはできません。
会社経営ができるビザ
- 経営・管理
経営管理ビザがなくても、次の在留資格を有している場合は会社設立が可能です。
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
会社経営ができないビザ
一方、以下のビザで日本国内に滞在している場合は、経営者として日本に中長期滞在し会社経営することはできません。
- 短期滞在
- 留学
- 家族滞在
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能 など
上記のビザを有していれば、起業準備のための活動は日本国内でできますが、会社設立後に役員報酬を得て代表取締役などの役員に就任し会社の経営や管理を行うことは、違法な資格外活動となります。これらのビザは、留学、家族滞在や会社で雇用されて働くための特定の活動を許可されたビザです。役員報酬をもらって日本国内で経営者として活動してしまうと不法就労になってしまいます。
そのため、日本国内で経営者として活動し経営管理をするには、会社経営ができるビザに変更をする必要があります。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで滞在している場合でも、小規模など、主なビジネスで活動が経営でなければ、一定の範囲で会社経営はできます。しかし、事業が軌道にのり、主な活動が経営者としての活動であれば、経営管理ビザに変更する必要があります。外国人の方は、会社を辞めてから起業準備する方がいますが、会社を辞めてしまうと就労ビザの目的としている活動をしていない期間が発生してしまうため、速やかに経営管理ビザに変更する必要があります。
短期滞在ビザでは、起業準備しかできない
外国人は短期滞在ビザでも、有効期間は3か月ですが、3か月以内に1回だけ日本に来日することができます。また、有効期間が長い数次短期滞在ビザを有していれば、数次短期滞在ビザの有効期間内であれば何度でも日本に短期間(一般的には90日間)来日することができます。
ただし、これらの短期滞在ビザでできる活動は、商談、契約、会議、業務連絡、宣伝、アフターサービス等のみです。短期滞在ビザで日本国内での起業準備をし、会社設立まではできます。しかし、役員報酬をもらって、日本国内で経営者として活動するには経営管理ビザが必要です。短期滞在ビザでは、日本で働いてお金を得る(就労活動)を認めていません。外国人が会社を設立し、役員報酬をもらわず経営者として活動するのであれば問題ないですが、役員報酬をもらうと不法就労となってしまいます。
役員報酬をもらいながら日本国内で実際に経営者として活動するには、会社設立後に速やかに経営管理ビザを取得する必要があります。
ビザ保証制度で当社がお手伝いした経営管理ビザ取得と会社設立を100%保証します
1-2.経営管理ビザ取得には、資本金500万円の用意と事業所の確保が必要
日本国内で会社を経営できるビザを有していなければ、経営管理ビザを取得する必要があります。経営管理ビザを取得する要件の一つとして事業規模が求められ、常勤職員2名以上又は資本金500万円以上いずれかと事業所の確保が必要です。
資本金500万円の用意
起業初期段階で常勤職員を雇用することは重い負担となるため、資本金として500万円以上を用意して経営管理ビザを取得することが一般的です。
資本金500万円は調達の経緯(出所)が審査される
経営管理ビザの500万円以上の資本金は調達経緯が審査の対象となります。資金がどのように集められたのかについて審査されます。形式だけの「見せ金」では認められません。
もし資本金を外国人の預貯金から捻出する場合、その資金が適切な収入源から蓄えられたものであることを裏付ける必要があります。その証拠としては、税務申告書、給与明細、銀行の取引記録などが挙げられます。また、親族や知人から借金した場合には、借用証を用意するなど、資金の出所を証明することが求められます。
資金の送金方法も審査される
海外から海外に資金源を持つ場合、その資金が日本国内に適法に転送されたことを証明する書類が求められます。送金履歴や銀行の取引証明がこれにあたり、送金過程で発生する可能性のある手数料や為替レート変動にも注意を払う必要があります。500万円以上の送金を明確に示す証拠を保持することが肝要です。
また、100万円を超える現金を国内に持ち込んだ際には、税関での申告が義務付けられています。この申告書類は、資本金として持ち込んだ現金が合法的に持ち込まれたことを証明する方法となります。
独立した事業所の確保
経営管理ビザを取得するためには、日本国内に実際にビジネスを行うための実体を持つオフィスを会社名で設けることが必要です。
事業所には、次の2つの基本要件を満たすことが必須です。
- 経済活動が一つの経営体の指揮のもと、一定の場所、つまり特定の区画で行われていること
- 財やサービスの生産や提供が、人員及び設備を用いて、継続的に実施されていること
これらの定義は、総務省によって設定された日本標準産業分類の一般原則における事業所の定義に準拠しています。
バーチャルオフィスは不適格
初期段階での固定費削減のためにバーチャルオフィスを検討するケースも多いですが、経営管理ビザを取得する上で、上記要件を満たす実際にビジネスが行われる事業所が必要であるため、バーチャルオフィスは適用外となります。
レンタルオフィスやシェアオフィスを利用する場合でも、共用スペースのみの利用は認められず、事業活動を行うための独立した区画が必要です。単にパーテーションで仕切られた空間は不十分です。
賃貸契約は法人名義、事業用途で契約する
賃貸借契約は法人名で行い、契約目的を事業用途(店舗やオフィスなど)に限定することが要求されます。住居用途での契約は不許可の対象です。また、短期賃貸や移動可能な施設の使用は、事業の継続性が問われるため認められません。
事業所には、電話、FAX、パソコン、コピー機などの基本的な設備を備える必要があり、経営管理ビザ申請時にはこれらの設備があることを証明する写真が求められます。
事業の種類や雇用する従業員数に応じた事務所の広さが求められます。製造業、教育塾、中古車貿易業などの事業では、事業所以外にも資材置き場や教室、車両置き場などのスペースを確保する必要があります。従業員を複数雇用する場合は、それぞれが働くためのスペースも確保する必要があります。
1-3.印鑑証明書又は署名(サイン)証明書を有すること
日本でビジネスをするには、会社設立と日本の銀行口座開設が必要です。それぞれのステップで、署名(サイン)証明書、印鑑証明書の提出が求められます。
会社設立時には印鑑証明書又は署名証明書が必要
会社設立登記をするときには、印鑑証明書が必要です。印鑑証明書がないときは、本国の役所又は公証役場で発行される署名(サイン)証明書で代用できます。署名(サイン)証明書とは、登記申請書などに記載する署名(サイン)が本物であることを示す書類です。日本に居住する外国人は、在日大使館や領事館で交付を受けられます。
印鑑証明書は不動産賃貸借契約など各種手続きで使う
印鑑証明書は、在留カードがあれば、住民票登録ができます。住民票登録できれば、印鑑登録が可能であるため印鑑証明書の発行が可能です。
また、日本国内で、会社を運営するための事業所を確保するためには、不動産の賃貸借契約が必要です。契約の際には、経営者自身の印鑑証明書や在留カード、パスポートなどの身分証明書を求められることがあります。このように各種手続きで印鑑を求められることが多いため、登録しておくと便利です。
1-4.日本の銀行口座を有すること
会社を設立するにあたっては、外国人が資本金を送金する際の受け皿となる個人の銀行口座が必要です。
日本の銀行の国内又は海外支店、外国の銀行の国内支店の個人口座が必要
銀行口座は、日本の銀行の日本国内又は海外支店の口座、外国の銀行の日本国内支店の個人口座を用意する必要があります。現在又は過去に日本に滞在しており、日本の銀行口座を有していればその個人口座を利用できます。
海外在住の外国人が日本に銀行口座を持っていない場合には日本の協力者が必要
海外居住の外国人が日本の個人口座を有していない場合には、会社設立ができません。短期滞在ビザで来日しても、日本の銀行は在留カードを持っていない外国人に対しては、個人口座の開設を受け付けてはくれません。
その場合には、日本国内の協力者に手伝ってもらい、会社設立時の発起人又は取締役になってもらい、協力者の個人の銀行口座を利用させてもらう必要があります。そして、会社設立関係の手続き完了後、協力者の方には退任してもらうという手続きが必要です。
2.経営管理ビザを取得するには?
外国人が日本国内で起業し経営するためには、日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等・定住者の在留資格、又は経営管理ビザを取得することが必要です。
経営管理ビザを取得するには、次の条件を満たした上で、出入国管理局に経営管理ビザを申請します。
2-1.事業規模(常勤職員2名以上又は資本金500万円以上)を満たしている
常勤職員2名(日本人又は定住者・日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等のうち、いずれかの在留資格を持つ外国人)以上を雇用している、もしくは資本金か出資総額が500万円以上で用意することが必要です。
2-2.事務所が確保されている
賃貸借契約書に、「事業用」として賃貸していることが記載されており、居住用スペースと一緒になっていないことが必要です。そのため、会社設立するためには、事務所や店舗などの事業所を事前に用意しておく必要があります。
また、経営管理ビザ申請時には、内装工事や什器備品もそろえておき、いつでも開業ができる状態にしておく必要があります。
2-3.事業の適正性・安定性・継続性を示せる
事業に安定性と継続性があり、経営者本人に経営能力があることを事業計画書などにより説明できる必要があります。
特に重要なのが、事業計画書です。日本における事業の見込み、収支計画などを事業計画書に記載し、安定・継続的なビジネスができることを事業計画書で説明できるようにしておく必要があります。すでに、日本国内での見込み客や仕入れルートなど取引先があれば取引先との契約書を用意しておくとよいでしょう。
2-4.事業の経営又は管理に実際に従事する
事業の経営に従事するとは、経営管理ビザ申請者自らが実際に会社経営をすることを指します。具体的には、重要実行の決定や業務の執行をする代表取締役、取締役になり、役員として実際に活動することです。また、事業の管理に従事するとは、支店長、工場長、部長などの会社の管理者につき、実際に管理業務に活動する必要があります。
3.外国人の会社設立と経営管理ビザ取得の流れ
経営管理ビザ取得を目指した、会社設立は次の流れで進めていきます。
- 会社の基本事項を決める
- 会社代表印を作成する
- 個人名義での事務所、店舗の確保(賃貸借契約等)
- 定款作成・公証人による定款認証
- 資本金を払い込む
- 会社設立登記の申請・完了
- 外為法の届出
- 個人から法人へ事務所の賃貸名義変更
- 開業届の提出
- 事務所・店舗の設備などの準備
- 許認可取得(必要な場合)
- 経営管理ビザを申請
- 外国人個人の住民票、印鑑登録を行う
- 経営活動開始(法人口座の開設、社会保険の加入)
会社設立と同じタイミングで、事業経営、そして、経営管理ビザを取得することを目指しているのであれば、経営管理ビザ取得の要件をみたした会社設立手続きを行う必要があります。
各ステップで実施することを紹介します。
会社設立後に将来的に経営管理ビザ取得を目指す場合
取り急ぎ、会社を設立し、日本にいる協力者もしくは、リモートで海外居住の外国人が会社経営を当面行い、将来的に日本に来日時に経営管理ビザを取得することを目標とする場合には、会社設立登記だけ行えば十分です。
その場合には、経営管理ビザを取得を目指す段階で、費用は掛かりますが、経営管理ビザ取得の要件を満たす会社に、事業所移転するなど設備投資をしていくことになります。
3-1.会社の基本事項を決める
会社の業種や事業目的、所在地、名称(商号)、発起人を決定します。同一所在地に同一名称の会社があるときは、登記ができないため注意は必要です。
なお、同一名称の会社とは、社名と会社の種類を含む名称全体が同じである会社を指します。
例えば、A株式会社と株式会社A、A株式会社とA合同会社は別の会社と判断されるため、Aという名称をすでに使用している会社があっても申請できます。
本店所在地に同一名称の会社が存在するかどうかは、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」の「商号調査」で調べることが可能です。定款を作成する前にチェックしておいてください。
3-2.会社代表印を作成する
会社代表印を作っておきます。特に決まりはありませんが、代表取締役印と角印、銀行印の3つを作成することが一般的です。
3-3.個人名義での事務所、店舗の確保(賃貸借契約等)
会社の基本事項が決まったら、次に行うことは事務所の確保です。
適切な事業所を選び、初めは個人名義で賃貸契約を結びます。法人として設立された後、賃貸契約の名義を個人から会社名義に変更することが一般的です。事務所を選ぶ際には、その場所が法人登記や在留資格の申請に適しているかどうか、「事業所要件」を満たしているかをしっかり確認することが大切です。
バーチャルオフィスや住所登録のみ、またオフィス兼住宅は避けてください。これらの要件を満たさない場所を事業所として進めると、設立後に別の場所に移転しなければならなくなり、時間や費用の面で負担が大きくなります。そのため、最初から注意深く事務所を選択することが重要です。
さらに、会社設立時には事務所の賃貸契約書が直接必要ではありませんが、将来的な問題を避けるためにも、貸主、不動産仲介会社と将来的に法人名義に変更することを伝えて、契約内容を確認してから設立手続きを進めましょう。口約束のみでた引退契約、会社設立を進め、後に貸主からクレームを言われ、転居しなければならない事態にならないよう、適切な準備を行い、スムーズな会社設立と運営を目指しましょう。
3-4.定款作成・公証人による定款認証
会社のルールをまとめた定款を作成します。作成後、会社の本店所在地の都道府県内にある公証役場にて、公証人による定款認証を受けます。なお、定款認定を申請するときには次の書類が必要です。
- 定款 3通
- 発起人全員の印鑑証明書 各1通
- 発起人全員の実印
定款認証には手数料と収入印紙代合計で10万円ほどの費用がかかります。ただし、社団法人や信用金庫の定款、司法書士や行政書士に依頼して作成した電子定款は、特定文書にかかる印紙税が不要なため、費用は6万円ほどです。
海外居住の外国人は印鑑証明書の代わりにサイン証明書を用意する
外国人が住む国に印鑑登録制度がない場合には、印鑑証明書の代わりに外国人のサインを証明するサイン証明書(宣誓供述書)を用意します。サイン証明書(宣誓供述書)を活用して、定款認証手続きが可能です。
本店所在地の公証役場に外国人本人が訪問できない場合には、司法書士や行政書士に定款作成を代理することで定款認証手続きをすすていくことができます。
3-5.出資金を払い込む
定款認証後、資本金を発起人が定めた銀行口座に払い込みます。払い込んだ証明書は会社設立登記に必要なため、大切に管理しておきましょう。
3-6.会社設立登記の申請・完了
会社設立登記の申請を法務局で行います。設立登記には登録免許税が15万円かかります。登記手続きは司法書士などに代行してもらうことも可能ですが、その場合は専門家報酬が必要です。
3-7.外為法の届出
発起人全員が日本に住所がない、非居住者の場合でも、会社設立登記を行うことは可能です。ただしその場合は、日本銀行を経由して、財務大臣と事業を所管する大臣に会社設立の届出を行わなくてはいけません。原則として、会社設立登記申請後に手続きを実施します。
事業内容などによっては、会社設立登記申請前に届出が必要なケースもあります。専門家に相談し、正しい順序で手続きを進めていきましょう。
3-8.個人から法人へ事務所の賃貸名義変更
会社設立登記後に会社謄本と印鑑証明書が取得できるようになります。この書類を事務所の貸主に提出して、個人名義で借りている事業所の名義を法人名義に変更する手続きを行います。経営管理ビザを申請するためには、法人名義の賃貸借契約書が必要なためです。
3-9.開業届の提出
会社設立登記完了後、本店所在地を管轄する税務署に開業届を提出します。
3-10.事務所・店舗の設備などの準備
経営管理ビザの申請時には、事業運営設備が整っている必要があります。
具体的には、事業運営に必要な最低限の設備としてパソコン、コピー機、電話、ファックスの設置が必須です。これらの設備が適切に準備されていることを、写真を添付して証明することが一般的です。また、審査過程では、実際の通信設備の確認のためにNTTへの照会が行われる場合があります。
加えて、郵便受けや看板、その他の標識の設置も重要です。顧客に対して、事業所の存在を示すために設置する必要があります。
3-11.許認可取得(必要な場合)
旅行業、古物商許可、免税店、人材紹介業など許認可が必要な事業を行う場合には、経営管理ビザ申請前に事前に許認可申請し、許認可取得をしておきます。
3-12.経営管理ビザを申請
事業所を確保し、内装工事や什器備品を揃え、事業スタートができる状態で経営管理ビザを申請します。ビザ取得後、外国人が来日し在留カードを受け取れば、経営活動をスタートできます。
3-13.外国人個人の住民票、印鑑登録を行う
在留カードを受け取れば、お住まいの地域の市区町村役場で住民登録が可能となります。住民登録後は、銀行や不動産など各種手続きに必要な住民票、印鑑証明書を取得できます。
3-14.経営活動開始(法人口座の開設、社会保険の加入)
ビジネスを運営していくうえで法人銀行口座の開設と社会保険の加入を行います。
特に法人口座開設については、銀行によって審査基準が異なり、特に外国人で経営経験がない場合、口座開設が難しいことがあります。大手銀行では1年間事業実績を求めららることから、実際に経営管理ビザを取得していても、外国人経営者による法人口座開設が難しいケースが多くあります。
ネット銀行の口座は比較的開設しやすいです。口座開設にあたっては、日本人や日本の銀行口座を持つ外国人などの協力者のサポートを受けて開設手続きを行うと比較的スムーズにできます。
4.外国人が会社を設立するときの必要書類
法務局で会社設立登記の申請手続きをするときは、次の書類等が必要です。
- 登記申請書(外国語のときは日本語訳をつける)
- 定款
- 資本金払込証明書
- 代表者・発起人の印鑑証明書かサイン証明書
- 印鑑届出書
それぞれの書類を準備するときの注意点を説明します。
4-1.登記申請書
会社設立登記の申請書は、法務局でも受け取れますが、法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。会社の種類によって申請書が異なるため、正しい申請書を取得して必要事項を記入しておきましょう。
4-2.定款
公証人による認証を受けた定款の謄本も必要です。ただし、合同会社を設立する場合は定款認証の必要がないため、作成した定款をそのまま提出できます。
なお、本店所在地を変更したときは、その都度、本店移転登記の手続きを実施しなくてはいけません。将来的に同一市区町村で本店を移転する可能性があるときは、定款の本店所在地の項目は市区町村までの記載に留めておきましょう。
4-3.資本金払込証明書
資本金を発起人の口座に払い込んだ証明書も必要です。なお、詳しくは後述しますが、資本金の払い込みに使用できる口座は日本の銀行に限られます。
4-4.代表者・発起人の印鑑証明書又はサイン証明書
代表者と発起人全員の印鑑証明書も必要です。印鑑証明書は定款認証の際にも必要なため、まとめて取得しておくといいでしょう。外国人の方が、日本で印鑑登録をしていない場合には、会社社設立登記はサイン証明書を取得して行うことができます。サイン証明書は本国の役所や公証役場、日本国内の在日大使館で取得します。
なお、署名(サイン)証明書を提出するときは、日本語訳も必要です。登記申請に際して外国語の書類を提出するときは各書類の日本語訳を取得しておきましょう。
なお、登記申請の際に使用できる印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のもののみです。定款認証から会社設立登記までに期間が空くときは、発行日を確認しておきましょう。
4-5.印鑑届出書
会社設立登記にあたっては、会社の実印(代表取締役印)を用意し、印鑑届出書を提出しておくと便利です。。
外国人代表者は会社代表印を登録しなくても、代表者のサイン証明書をつければ設立登記は可能ですが、会社の印鑑証明書の発行を受けることができません。
会社実印を登録すると、以後、法務局での会社登記手続きで都度サイン証明書を用意することなく会社代表印で登記することできるようになるほか、会社の印鑑証明書を発行することができるようになるメリットがあります。会社代表者の印鑑証明書は以後、日本国内でのビジネスで使う書類となるため、必ず会社の印鑑届出登録をするようにしましょう。
5.外国人が会社設立登記をするときの注意点
外国人が日本で会社設立登記をするときは、次の3つのポイントを確認しておきましょう。
- 資本金払込口座が日本の銀行であるか?
- 在留資格が適切であるか?
- 経営管理ビザを取得予定の場合には、要件を満たした会社内容となっているか?
いずれか1つのポイントでも満たしていないときは、会社設立登記がスムーズにできなくなります。
設立登記申請、経営管理ビザ申請する前に確認し、対処策を講じておきましょう。
5-1.資本金払込口座が日本の銀行であるか?
資本金払込口座は、日本の銀行法が規定する金融機関の口座でなくてはいけません。
日本の銀行法で規定する金融機関とは、日本に本店があり日本で登録している金融機関です。そのため、資本金払込用の口座が日本の金融機関の銀行口座を発起人がもっているか確認しておきましょう。
発起人の口座が海外銀行のとき
発起人が海外の銀行口座しかもっていなければ資本金払込用の口座がない状態のため、日本国内で会社設立登記をすることはできません。ただし、発起人の口座が海外銀行のものであっても、その銀行が日本国内に支店をもっており、その日本国内の支店の口座をもっていれば、資本金払込口座として活用することができます。
発起人の口座が日本の銀行の海外支店のとき
発起人の口座が、日本の銀行法で規定する日本の金融機関の海外支店のものであるときは問題ありません。資本金払込口座として適切なため、払込証明書を取得して登記手続きを進めていきましょう。
ただし、海外支店の口座では、取引のレートが海外通貨の可能性があります。その場合は、日本円でどの程度の資本金を振り込んだのかがわかるように、レートを証明する書類も必要です。口座のある金融機関にレート証明書の発行を依頼しましょう。
資本金払込口座を用意できないとき
会社設立にあたって、日本国内に発起人の個人口座を事前に開設する必要があります。口座開設には日本に住民票を取得していることや、滞在期間が6ヵ月を超えていることなどを求められることがあります。事前に金融機関に問い合わせておきましょう。
海外居住者が経営管理ビザをこれから取得して来日し、起業する場合には事前に口座開設することは難しい状況です。そのため、先述した通り日本国内で銀行口座を持っている人に依頼し、協力者に発起人又は取締役になってもらい、協力者の方の銀行口座を利用させてもらうことも方法の1つです。そして、会社設立関係の手続き完了後、協力者の方には退任してもらいます。
5-2.在留資格が適切であるか?
既に日本で就労している外国人が日本で会社を設立し、会社経営者になるときは、定住者・日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等のうち、いずれかの在留資格が必要です。いずれの在留資格も持たないときは、経営管理ビザが必要です。経営管理ビザ以外のときは、事前に入国管理局で経営管理ビザへの変更手続きを済ませておく必要があります。
5-3.経営管理ビザを取得予定の場合には、要件を満たした会社内容となっているか?
経営管理ビザを取得するためには、これまで述べてきたような事業所確保、事業規模などの要件を満たす必要があります。仮に、会社設立登記の内容が経営管理ビザ取得要件を満たしていない場合には、変更手続きが必要となり余分な追加費用が発生する可能性があります。
会社設立と経営管理ビザに詳しい専門家に相談しながら手続きを進めていくことでスムーズな会社設立をスタートすることができます。
6.まとめ
本記事では、外国人が会社設立登記をするときに知っておきたい事柄について解説しました。
内容をまとめると、以下のとおりです。
| ✓ 外国人が日本で会社を設立し、日本で会社経営するときは、海外居住で経営する場合はビザがいらないが、日本に中長期滞在して会社経営するには経営管理ビザや永住権などが必要
✓ 日本でビジネスを始めるためには、会社設立と銀行口座が必要であり、それぞれの手続きで署名(サイン)証明書、印鑑証明書が必要となる ✓ 経営者として経営管理ビザ取得するには、①事業所が日本国内に確保されていること、②一定以上の事業規模(常勤職員2名以上又は資本金500万円以上)を満たすこと、③事業の適正性・安定性・継続性を示せること、④事業の経営に実際に従事することの4つの要件がある ✓ 日本で会社設立するには、先に会社設立登記をし、日本拠点で事業開始ができる状態となったあとに、経営管理ビザを申請するという手順が必要 |
外国人も日本人と同様、日本国内で会社を設立することは可能です。ただし、定住者・日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等のうち、いずれかの在留資格を持つか、「経営・管理」ビザを有していることが求められます。実際のところ、日本在住でなくても会社を設立できますが、その場合は、日本銀行を経由して財務大臣と事業を所管する大臣に会社設立の届出を行わなくてはいけません。
出資金を払い込む金融機関にも制限があります。日本の銀行法で規定する金融機関の口座以外は、出資金払込口座には使用できないため注意しましょう。
会社設立登記の手続きは、司法書士に相談できます。不備なく手続きを進めるためにも、専門家に依頼しましょう。
この記事の監修

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)
相談実績5000件超、実務経験10年以上の経験を持つ司法書士。
海外にまつわる相続やビジネスに関する法律、契約書作成、コンプライアンスに関するアドバイスなど、幅広い分野に対応。近年は、当事者の一部が海外に居住するケースなど国際相続の相談が多く、精力的に取り組んでいる。