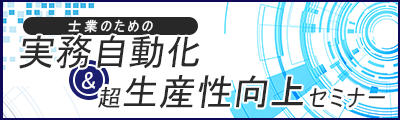近年、国際化の進展に伴い、外国籍の方が当事者となる相続案件に直面する機会は、我々専門家にとって決して珍しいものではなくなりました。中でも、日本に居住する中国籍の方(在日中国人)の相続手続きは、その人口の多さや経済的な結びつきの強さから、実務上、遭遇する頻度が比較的高い類型の一つと言えるでしょう。
しかし、いざ受任してみると、まず「どの国の法律が適用されるのか」という準拠法の問題で立ち止まり、次に「どうやって相続人を確定するのか」という戸籍制度の違い、すなわち「公証書」をどうするのかを検討していく必要があります。
- 在日中国人の相続では、財産の種類(不動産か動産か)により、準拠法が日本法と中国法に分かれる可能性がある。
- 相続の準拠法(例:日本法)と、相続人たる身分関係の準拠法(例:中国法)は、通則法上、別個に検討する必要がある。
- 中国法が準拠法となる場合、相続人の範囲(「父母」が第1順位)や、夫婦共有財産の清算に留意する。
- 中国には日本の戸籍制度が存在せず、戸口簿では足りないため、相続関係の証明は「公証書」が必要となる
- 中国在住の相続人がいる場合、日本の印鑑証明書の代替として、中国の公証処で「署名認証(声明書)」等を取得する必要がある
本記事では、我々専門家が在日中国人の相続(特に日本国内財産)を取り扱う上で直面する「準拠法」と「公証書」という論点を取り上げ、実務的な対応方法を解説します。
目次
1.相続準拠法の原則と例外
在日中国人の相続案件を受任した際、専門家が最初に行うべきは、その相続全体、および各財産に適用される法律(準拠法)の確定です。この判断を誤ると、その後の相続人確定や必要書類の収集がすべて無駄になってしまいます。
1-1.原則:被相続人の本国法(通則法36条)
まず原則に立ち返ると、日本の「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」)第36条は、「相続は、被相続人の本国法による。」と定めています。
したがって、被相続人が亡くなるまで中国籍であった場合、形式的には中国の法律が相続準拠法となると考えられます。
しかし、ここで中国の国際私法(渉外民事関係法律適用法)の規定を確認する必要があります。中国法では、相続について以下のように定められています。
・動産:被相続人の死亡時の住所地法による
・不動産:不動産所在地法による
このように、被相続人の本国法(中国法)が、財産の種類によって「住所地法」や「所在地法」を参照するよう指定しているため、通則法36条の「本国法による」という規定が、最終的にどの国の法律を指すのかを改めて検討する必要があります。
1-2. 在日中国人の財産別準拠法(日本国内財産)
この日中間の法律に基づき、在日中国人が日本国内に有する財産に当てはめて整理します。
| 財産 (種類と所在地) |
法的根拠 (日本の通則法 → 中国の国際私法) |
【結論】準拠法 |
| 不動産 | 通則法36条(本国法) → 中国法(所在地法) |
不動産の所在地が日本なら日本法、 不動産の所在地が中国なら中国法 |
| 動産 (預金等) |
通則法36条(本国法) → 中国法(住所地法) |
住所が日本なら日本法(反致)、 住所が中国なら中国法 |
ケース1:日本の「不動産」 → 所在地法=日本法
日本の不動産については、中国法が「不動産所在地法」によるとしているため、通則法36条を介して「日本の法律」が適用されることになります。これは実務上、比較的判断に迷いがない部分です。
ケース2:日本の「動産(預金等)」 → 住所地法(※)
一方、日本の銀行預金などの動産については、中国法が「住所地法」によるとしています。
ここで実務上の論点となるのが、「住所」の認定です。実務上、「ほとんどのケースで日本の法律が適用される」と単純化して説明されがちですが、厳密には、被相続人である在日中国人の「住所」がどこにあったかで結論が変わる可能性があります。
① 被相続人の「住所」が中国にあると認定される場合
この場合、中国法が指定する「住所地法」は「中国法」となり、日本の動産であっても、その相続は中国法に基づいて行われることになります。
② 被相続人の「住所」が日本にあると認定される場合
この場合、中国法が指定する「住所地法」は「日本法」となります。これは法学上「反致(はんち)」(通則法41条)が成立する典型的なケースであり、結果として日本の動産についても「日本法」が適用されることになります。
多くの在日中国人の方は、生活の本拠を日本に置いている(=住所が日本にある)ケースが多いため、結論として日本の動産についても日本法が適用される場面が多いのは事実です。
しかし、我々専門家としては、常に「被相続人の法的な住所はどこか」という論点を意識し、預金解約等の手続きにおいて金融機関から準拠法に関する見解を求められた際に、この法的構成を説明できるように準備しておく必要があります。
2.準拠法別に見る相続人の範囲と相続分
準拠法が確定したら、次はその法律に基づいて「誰が相続人になるのか」「相続分はどうなるのか」を確定します。
2-1.準拠法が「日本法」となる場合
準拠法が日本法と確定した場合、相続人の範囲と法定相続分は、日本民法の規定(配偶者は常に相続人、血族相続人の順位と法定相続分)に従うことになります。
ただし、ここで極めて重要な実務上の論点があります。それは、「相続の準拠法」と「相続人たる身分関係の準拠法」は別問題であるという点です。
ある者が相続人となるためには、「被相続人の子である」「被相続人の配偶者である」といった有効な身分関係が前提となります。そして、その身分関係が有効に成立しているか否かは、通則法の婚姻や親子の章(例:通則法24条~35条)によって別途判断されます。
ここで論点となるのが、「継子(連れ子)」や「事実婚の配偶者」の扱いです。
・【論点】継子(連れ子)の扱い
日本法が相続準拠法である場合、被相続人の配偶者の連れ子(継子)は、被相続人と養子縁組をしていなければ相続人になりません。 しかし、その「親子関係の成立」自体は、例えば通則法30条(準正)などが適用される結果、子の本国法(中国法)等で判断される可能性があります。
中国法では、扶養関係にあった継子との間に、養子縁組がなくとも親子関係の成立を認め、実子と同じ相続権を認める(中華人民共和国民法典第1072条)とされています。 したがって、相続の準拠法は日本法であっても、相続人を確定する前提としての身分関係の判断において中国法が適用され、結果として日本では相続権が認められないはずの継子が相続人として登場する可能性を、専門家としては常に念頭に置く必要があります。
・【論点】事実婚の配偶者の扱い
同様に、事実婚の配偶者についても、婚姻の成立に関する準拠法(例:通則法24条)の判断次第では、中国法に基づき法定相続人として認められます。
2-2. 準拠法が「中国法」となる場合
次に、前述のケース(被相続人の住所が中国にあると認定された場合など)で、日本の預金について中国法が準拠法となった場合の規定を確認します。これは日本の専門家にとっては馴染みが薄いため、特に注意が必要です。
・相続人の範囲:第1順位(配偶者・子・父母)
最大の特徴は、相続順位です。中国法では、第1順位が「配偶者・子・父母」とされています。日本民法では第2順位である「父母」が、子と同順位で第1順位に含まれます。
第1順位の者が一人もいない場合に、初めて第2順位(兄弟姉妹、祖父母)が相続人となります。
・法定相続分:同一順位間では「均等」が原則
日本の民法のように「配偶者2分の1、子2分の1」といった画一的な定めはなく、同一順位の相続人間では「均等」が原則とされています。
・遺留分制度はなし(ただし、扶養義務等の配慮規定あり)
日本のような遺留分制度はありません。ただし、遺産分配に際しては、扶養義務の有無や、生活に困窮し労働能力を欠く相続人への配慮が求められるなど、日本の制度とは異なる調整が行われます。
・【実務上の注意点】夫婦共有財産の清算
中国法では、特段の契約がない限り、婚姻期間中に得た財産は夫婦共有財産とされます。 これは、被相続人の名義となっている財産(例:日本の銀行預金)であっても、その半分は配偶者固有の財産であり、そもそも遺産相続の対象とはならない可能性が高いことを意味します。
したがって、中国法が準拠法となる動産については、まず夫婦共有財産の清算を行い、残りの持分(通常は2分の1)のみを遺産として、第1順位の相続人(配偶者・子・父母)で均等に分割する、という手続きを経る可能性があります。
3.「戸籍がない」をどうカバーするか?
準拠法と相続人が確定したところで、実務は最大の難関である「必要書類の収集」に移ります。日本の相続手続きが戸籍謄本・除籍謄本という高度に整備されたシステムに依存しているのに対し、中国にはこれに相当する制度が存在しません。
3-1. 中国の「公証書」とは何か
・日本の戸籍制度と中国の「戸口簿」制度の違い
しばしば日本の戸籍と比較されるものに、中国の「戸口簿(戸口登記簿)」があります。しかし、これは元々、住民登録や行政管理を主目的とするものであり、身分関係の変動(出生、結婚、死亡、親族関係など)を公的に証明する機能は、日本の戸籍に比べて限定的です。
・なぜ「戸口簿」だけでは相続手続に不十分なのか
日本の法務局や金融機関が要求する「被相続人の出生から死亡まで」や「相続人全員」を証明する資料として、「戸口簿」だけでは全く不十分です。 この「戸籍がない」というギャップを埋めるのが、「公証書(こうしょうしょ)」という制度です。
これは、中国本国の「公証処(公証役場)」に所属する「公証員」が、申請に基づき、特定の事実(例:出生の事実、婚姻の事実、死亡の事実、親族関係など)や法律行為を証明するために作成する公文書です。 渉外相続実務においては、この「公証書」こそが、戸籍謄本の代わりとなる最も重要な証明書類となります。
3-2.相続手続きで必要となる主な公証書
日本の登記(不動産)や預金解約(動産)手続きで、一般的に必要とされる公証書は以下の通りです。事案に応じて、このうち必要なものを組み合わせて収集します。
① 死亡公証書:被相続人の死亡の事実を証明します。
② 出生公証書:相続人各自の出生の事実(=親が誰であるか)を証明します。
③ 結婚公証書:被相続人と配偶者の婚姻の事実を証明します。
④ 親族関係公証書:被相続人を中心として、配偶者、子、父母など、相続関係者全員の身分関係を一覧で証明するものです。実務上、これが最も中核的な書類となることが多いです。
⑤ (場合により)相続放棄の公証書:相続放棄をした者がいる場合に必要となります。
3-3.公証書の取得手続きの流れと翻訳
・申請場所:中国本国の「公証処(公証役場)」
これらの公証書は、原則として、その証明対象となる事実が発生した地域(例:出生地、婚姻届出地)や、当事者の住所地を管轄する中国本国の「公証処」で申請する必要があります。
これは、日本にいる相続人や専門家にとって、非常に大きな負担となります。現地(中国本土)の親族や専門家の協力なしに進めることは困難なケースがほとんどです。
・翻訳:日本での手続きには日本語の翻訳文が必須
当然ながら、公証書はすべて中国語で作成されます。日本の法務局や金融機関に提出する際は、日本語の翻訳文を添付する必要があります。
4.遺産分割協議と登記・預金解約の実務
必要書類の収集と並行し、最終的な手続きの準備を進めます。
4-1. 遺言書がある場合の対応
遺言の方式については「遺言の方式の準拠法に関する法律」に基づき、行為地法(日本)や本国法(中国)、住所地法(日本)など、いずれかの法律に適合していれば有効とされます(同法第2条)。
したがって、在日中国人が日本の方式(例:自筆証書遺言、公正証書遺言)で作成した遺言書も有効です。自筆証書遺言であれば、日本法に基づき家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
4-2. 相続人が中国在住の場合の「印鑑証明書」の対応方法
遺産分割協議を行う際、日本国内の相続手続きでは、遺産分割協議書への実印の押印と印鑑証明書の添付が要求されます。
しかし、相続人の一部(または全員)が中国在住で、日本に住民登録がない場合、日本の印鑑証明書を取得できません。この場合の代替手段として、実務上、主に以下の二つの方法が用いられます。
・代替手段1:遺産分割協議書への「署名認証(声明書)」
中国の公証処において、相続人本人が公証員の面前で遺産分割協議書(またはそれに準ずる「声明書」)に署名し、その署名が本人のものであることを公証員に認証してもらう方法です。これが印鑑証明書の代わりとなります。
・代替手段2:「署名(印影)公証書」
遺産分割協議書への認証とは別に、「本人の署名(または印鑑)はこれに相違ない」という事実を単独で証明する公証書を作成してもらう方法です。
実務上は、提出先機関(特に金融機関)が「代替手段2」の場合、公証書上の署名(印影)と遺産分割協議書上の署名(印影)の同一性判断を嫌うケースがあります。
4-3.登記申請・預金解約の必要書類まとめ
最終的に、日本の法務局(相続登記)や金融機関(預金解約)に提出する書類は、概ね以下のようになります。(事案により増減します)。
・公証書 (例:死亡公証書、親族関係公証書、出生公証書、結婚公証書など)
・上記公証書の日本語翻訳文
・死亡を証する書面 (日本国内で死亡した場合:死亡届記載事項証明書、死亡診断書の写し など)
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
-日本在住者:日本の市区町村発行の印鑑証明書
-中国在住者:上記2.で解説した「署名認証(声明書)」など
・相続人の本人確認書類(在留カード、パスポートの写しなど)
・(その他、固定資産評価証明書、預金通帳など財産資料)
5. まとめ
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]