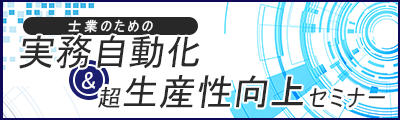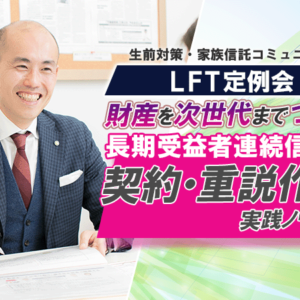先生方もご存知の通り、2025年6月10日、法務省の法制審議会-民法(成年後見等関係)部会が、成年後見制度の見直しに関する「中間試案のたたき台」を取りまとめました。これは、平成11年の成年後見制度創設以来の、まさに大改正に向けた具体的な第一歩であり、我々専門家の実務に影響を及ぼすものです。
「一度、後見が開始すると、本人の判断能力が回復しない限り終われない」
「後見人の権限が画一的で、本人の状態に合わせた柔軟な支援がしにくい」
「本人の意思よりも、画一的な財産保護が優先されがちではないか」
このような課題は、多くの先生方が実務の中で一度は感じたことのある「もどかしさ」ではないでしょうか。今回の見直しは、こうした現場の課題や、社会の変化、そして「本人の自己決定権の尊重」という大きな流れに応えようとするものです。
特に、私たちが注力している家族信託の分野においても、この改正は決して無関係ではありません。むしろ、任意後見制度との関係性の見直しなどを通じて、信託と後見の連携や役割分担が大きく変わる可能性があります。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
【成年後見制度見直しの中間試案のポイント】
- 「出口」の新設: 保護の必要性がなくなれば後見を終了できる。
- 「類型」の見直し: 現行3類型から、必要な権限を個別に付与する柔軟な制度へ。
- 「自己決定権」の徹底: 本人の同意を開始要件とする方向へ。
- 「交代」の円滑化: 「本人の利益のため」に後見人の交代がしやすくなる。
【実務への影響】
- 家族信託、任意後見との併存: 任意後見と法定後見の併存により、複合的な支援設計が可能に。
- 提案能力の高度化: 法定後見と信託、それぞれの長所を理解し、最適な提案が不可欠に。
- 後見人としての役割変化: 「管理者」から「支援者」へ。
- チーム支援の重要性: 他の専門職や関係機関との連携能力が必須に。
本記事では、相続や家族信託、成年後見業務に取り組む司法書士・行政書士、税理士、弁護士などの先生方に向けて、この中間試案の概要を解説するとともに、今後の実務にどのような影響が考えられるのか、特に「家族信託」と「成年後見」の2つの観点から深く考察します。2026年度の法改正を目指すとされるこの大きな変革の波に乗り遅れることのないよう、今のうちからその全体像と本質を掴んでいきましょう。
目次
1.なぜ今、成年後見制度の大改正が議論されるのか?その背景
今回の見直しがなぜこれほど大きなテーマとなっているのか、まずはその背景から確認しましょう。理由は一つではなく、複合的な要因が絡み合っています。
(1)超高齢社会の深化と認知症高齢者の増加
日本は世界でも類を見ない超高齢社会に突入し、認知症の方も増加の一途をたどっています。判断能力が不十分な方を支える成年後見制度の重要性は、ますます高まっているのです。
(2)「自己決定権の尊重」と国際的な潮流
2014年に日本が批准した「障害者の権利に関する条約」は、今回の見直しに大きな影響を与えています。この条約では、障害者が他の者と平等に自己の意思決定を行う能力を認められる権利が謳われています。
これを受け、従来の「本人の保護」に偏りがちだった制度から、本人の意思や選好を最大限尊重する「意思決定支援」へと、制度の基本理念を転換する必要性が強く認識されるようになりました。
(3)現行制度の課題と利用の低迷
現行制度は、一度開始すると本人の判断能力が回復しない限り終了できない「終わりのない制度」としての側面や、後見類型に利用が偏重し、本人の行為能力が画一的に制限されるという硬直性が指摘されてきました。こうした使い勝手の悪さから制度の利用は伸び悩み、本当に支援が必要な人に制度が届いていないという実態がありました。
これらの背景が複雑に絡み合い、今回の25年ぶりとなる大改正の議論へと繋がっているのです。
2.中間試案の衝撃!主要な改正ポイントを徹底解説
それでは、いよいよ中間試案の具体的な中身に入っていきましょう。まだ「たたき台」の段階であり、複数の案が併記されています。いずれも案の段階で確定ではありませんが、議論の方向性を理解することが重要です。ここでは特に実務への影響が大きいと思われるポイントに絞って解説します。
(1)最大の注目点!「法定後見の終了」規定の新設
今回の試案で最も注目すべきは、法定後見の「終了」に関する新たな規律が盛り込まれた点です。
現行法では、一度後見等が開始されると、本人の判断能力が回復しない限り、制度の利用をやめることはできません。しかし、試案では、本人の事理弁識能力が回復しない場合でも、「保護の必要性がなくなった」と家庭裁判所が判断した場合には、申立てにより審判を取り消す(終了させる)ことができるようになります。
これは実務上、非常に大きな変革です。例えば、遺産分割協議や不動産売却のために後見を開始したケースで、その目的が達成された後には、本人の生活状況等に応じて後見を終了させる、という選択肢が生まれるのです。
さらに、制度利用の形骸化を防ぐため、「法定後見に係る期間」を設けるかどうかも論点となっています。これについては、以下の3つの案が提示されています。
【甲案】
現行法を維持し、期間は設けない。
【乙1案】
保護者に権限を付与する各審判の際に、家庭裁判所が個別に有効期間を定める。期間満了前に更新の申立てがなければ効力が失われる。
【乙2案】
法定後見の開始から一定期間ごとに、保護者が家庭裁判所に「法定後見の要件の存在に関する報告」を義務付ける。その報告等に基づき、家裁が職権または申立てにより終了させることができる。
甲案(現行維持)を含む3案が並列的に検討されている状態ではありますが、「出口」が設けられることで、成年後見制度は「一生続く重い制度」から、「必要な時に、必要な期間だけ利用する柔軟なツール」へと変貌を遂げる可能性があります。
(2)後見・保佐・補助の「類型」はどうなる?
現行の「後見」「保佐」「補助」という3類型についても、抜本的な見直しが検討されています。
・【甲案】現行の3類型を維持しつつ、所要の修正を加える案
最も穏当な案です。類型の枠組みは維持しつつ、期間の設定や同意権の範囲の見直しなどで柔軟化を図ります。
・【乙1案】3類型を廃止し、必要な権限を個別に付与する「単一類型」案
最も抜本的な案です。本人の事理弁識能力の程度で類型を分けることをやめ、「事理弁識能力が不十分である者」を対象とし、「保護者の同意を要する旨の審判」や「保護者に代理権を付与する旨の審判」を、必要な法律行為について個別に、オーダーメイドで付与していくイメージです。
・【乙2案】「保護A」と「保護B」の2段階に再編する案
乙1案に近いですが、特に判断能力が低い層への対応を分けた折衷案です。
○保護A(事理弁識能力が不十分な者)
上記の乙1案と同様に、必要な権限を個別に付与します。
○保護B(事理弁識能力を欠く常況にある者)
開始審判により、現行の後見に近い包括的な代理権や取消権が保護者に付与されます。
どの案が採用されるかによって、我々の申立て実務や後見人としての職務内容は大きく変わります。特に乙1案や乙2案が採用された場合には、成年後見制度が柔軟な制度へと変容し「どの法律行為について、どのような権限が必要か」を具体的に検討する、よりコンサルティング能力が求められることになる可能性があります。
(3)本人の意思をどう尊重するか?「自己決定権」の徹底
今回の見直しの根幹をなすのが「本人の意思の尊重」です。中間試案では、これを具体化するための方策が随所に盛り込まれています。
・開始要件としての本人の同意
現行法では後見や保佐の開始に本人の同意は不要ですが、試案では原則として本人の同意を要件とする方向で議論されています。また、本人が明確に「異議」を述べた場合は開始できないとする案も提示されており、本人の意思に反した後見開始は、より抑制的になる方向です。
・保護者選任における本人の意見の重視
保護者を選任する際、「本人の意見」を考慮要素の冒頭に規定するなど、さらに重視する姿勢を明確にすることが検討されています。
・保護者の義務としての意思尊重
保護者の義務として、取消権を行使する際にも本人の意思を尊重しなければならないことを明確化するなど、権限行使のあらゆる場面で本人の意思が羅針盤となるべきことが示唆されています。
(4)柔軟な対応へ!「保護者の交代」の円滑化
「一度選任された後見人と相性が悪いが、不正行為でもない限り交代できない」というのも、実務上の大きな課題でした。試案では、現行の解任事由に加え、「本人の利益のために特に必要がある場合」を念頭に置いた、より柔軟な解任事由を新たに設けることが検討されています。これにより、後見人と本人・親族との信頼関係が破綻したケースや後見人の専門性の不足等により本人の生活・財産管理に支障がでているケースなどで、後見人の交代がしやすくなることが期待されます。
3.【実務への影響①】家族信託との関係はどう変わるか?
ここからは我々司法書士・行政書士など相続専門家の実務に直結する影響について、特に「任意後見」「家族信託」との関係に焦点を当てて考察します。
(1)「任意後見」と「法定後見」の併存容認がもたらす変化
中間試案の「第6 任意後見制度と法定後見制度との関係」では、極めて重要な論点として、任意後見人と法定後見の保護者の併存を認めるかどうかが提示されています(【乙案】)。
現行法では両者の併存は原則認められず、法定後見が開始されると任意後見契約は終了してしまいます。しかし、もし【乙案】が採用され両者の併存が認められるようになれば、実務は大きく変わります。
・任意後見契約を「ベース」に、不足分を法定後見で「上乗せ」する設計が可能に。
例えば、本人の信頼する長男を任意後見人としつつ、取消権や同意権が必要になった場合にのみ、専門職を(法定後見の)保護者として選任し、その権限だけを付与してもらう、といった柔軟な対応が可能になります。
・家族信託との連携がよりスムーズに。
現状でも「財産管理は家族信託、身上保護は任意後見又は成年後見」という組み合わせは有効です。これに併存可能な法定後見制度が加われば、信託契約でカバーできない法律行為、身上監護や不測の事態が発生した場合に、信託契約を維持したまま、法定後見のスポット的な支援を追加できます。これにより、「信託」「任意後見、(必要に応じて)法定後見」という、より顧客に対して選択肢がある財産管理体制を構築・提案できる可能性があります。
併存を容認する【乙案】が採択されれば、本人が選んだ任意後見人をベースにしつつ、必要時のみ専門職を法定後見の保護者として追加できる という柔軟な設計が可能になる半面、権限分担が複雑になり、金融機関など第三者が判断に迷う恐れや責任の所在が不明確になるのではないかといった懸念もあり、今後のパブリックコメントを経てどの案が採択されるかが、実務に直結する注目点と言えるでしょう。
(2)「意思決定支援」重視の流れと信託実務
今回の改正が「本人の意思決定支援」を強く打ち出している点は、家族信託の実務にも影響します。家族信託は本人の意思に基づく自己決定の実現ツールですが、本人の判断能力低下後、受託者が本人のためにどのような財産管理・給付を行うべきか、判断に迷う場面も少なくありません。
改正後の後見制度で保護者の「意思決定支援義務」が明確化されることは、信託における受託者の役割を考える上でも大きなヒントになります。我々専門家は、信託契約を設計する際に、単に財産管理の方法だけでなく、将来、受託者が本人の意思をどう推し量り実現すべきか、そのプロセスについても契約書に盛り込むなど、「本人の最善の利益」とは何かをより深く突き詰める姿勢が求められます。
(3)法定後見の利用しやすさが信託の選択に与える影響
法定後見制度が「使いやすく、柔軟で、終わりがある」制度に変われば、これまで後見を敬遠して家族信託を選択していた層が、法定後見を選ぶ可能性も考えられます。特に、解決すべき課題が限定的な場合、改正後の法定後見は非常に魅力的な選択肢となり得ます。
しかし、信託には後見制度にはない「資産承継」の機能や、裁判所の関与を必要としない「迅速性・柔軟性」という大きなメリットがあります。改正後も、法定後見制度を利用、終了するにあたってはその要件を満たすほか、法定後見制度利用中における家庭裁判所への報告、相談が必要となることが想定されることから、柔軟な財産管理を期待するのは難しいかもしれません。
重要なのは、我々専門家が、改正後の成年後見制度と家族信託、それぞれの長所・短所を正確に理解し、顧客の状況に応じて最適なツールを提案できる能力です。
4.【実務への影響②】成年後見実務はこう変わる!
次に、我々が後見人等として職務を行う「成年後見実務」への影響を具体的に見ていきましょう。
(1)後見人としての権限と義務の再定義
法定後見の「類型」が見直されれば、我々の権限も大きく変わります。【乙1案】や【乙2案】が採用された場合、もはや「後見人だから包括的な代理権がある」という時代は終わり、「どのような法律行為について、代理権や同意権が付与されているのか」を個別に確認し、その範囲内で職務を遂行することが求められます。権限の範囲外の行為をうっかり行ってしまうリスク管理が重要になる一方、責任範囲が明確になり、業務負担が軽減される側面もあるかもしれません。
(2)報酬体系への影響は?
報酬体系が直接変更されるわけではありませんが、試案では報酬判断の考慮要素として「保護者が行った事務の内容といった考慮要素を明確にする」ことが検討されています。また、最高裁は報酬付与額の実績データを詳細に公表していく方針を示しており、報酬算定の透明性と予測可能性が高まることが期待されます。「どのような事務を行えば、どの程度の報酬が見込まれるのか」が明確になれば、専門職として後見業務を受任する際の判断材料にもなります。
(3)後見人の交代と「チーム支援」の重要性
保護者の交代が柔軟になることは、我々専門職に良い緊張感をもたらします。本人や親族とのコミュニケーションを怠り、信頼関係を構築できなければ、交代を求められるリスクが高まるからです。これは、我々が単なる「事務処理代行」ではなく、本人や家族に寄り添う「コーディネーター」としての役割を担うべきことを示唆しています。今後は、医療・介護・福祉の関係者などと「支援チーム」を形成し、その中で専門職としての役割を的確に果たしていく能力が不可欠となります。
5.まとめ
ここまで、成年後見制度改正の中間試案の概要と、我々の実務への影響について考察してきました。最後に、要点をまとめます。
【成年後見制度見直しの中間試案のポイント】
- 「出口」の新設: 保護の必要性がなくなれば後見を終了できる。
- 「類型」の見直し: 現行3類型から、必要な権限を個別に付与する柔軟な制度へ。
- 「自己決定権」の徹底: 本人の同意を開始要件とする方向へ。
- 「交代」の円滑化: 「本人の利益のため」に後見人の交代がしやすくなる。
【実務への影響】
- 家族信託、任意後見との併存: 任意後見と法定後見の併存により、複合的な支援設計が可能に。
- 提案能力の高度化: 法定後見と信託、それぞれの長所を理解し、最適な提案が不可欠に。
- 後見人としての役割変化: 「管理者」から「支援者」へ。
- チーム支援の重要性: 他の専門職や関係機関との連携能力が必須に。
この中間試案は、6月下旬にもパブリックコメントに付され、広く意見が募られます。その後、さらなる議論を経て、2026年度の法改正を目指すスケジュールであり、内容はまだ何も確定してはいません。だからこそ、私たち専門家は、この中間試案の内容を深く理解し、実務の視点から、成年後見制度、家族信託をどのように活用していくのか、将来を見据えたアドバイスを顧客に対して行っていく必要があります。
今回の改正は、成年後見制度の歴史における大きな転換点であり、我々司法書士・行政書士の業務のあり方そのものを問い直すものです。私としても、引き続きこの動向を注視し、先生方と情報を共有しながら、来るべき新時代に備えていきたいと考えております。
家族信託契約書を作成する際にどのように設計・起案していますか?
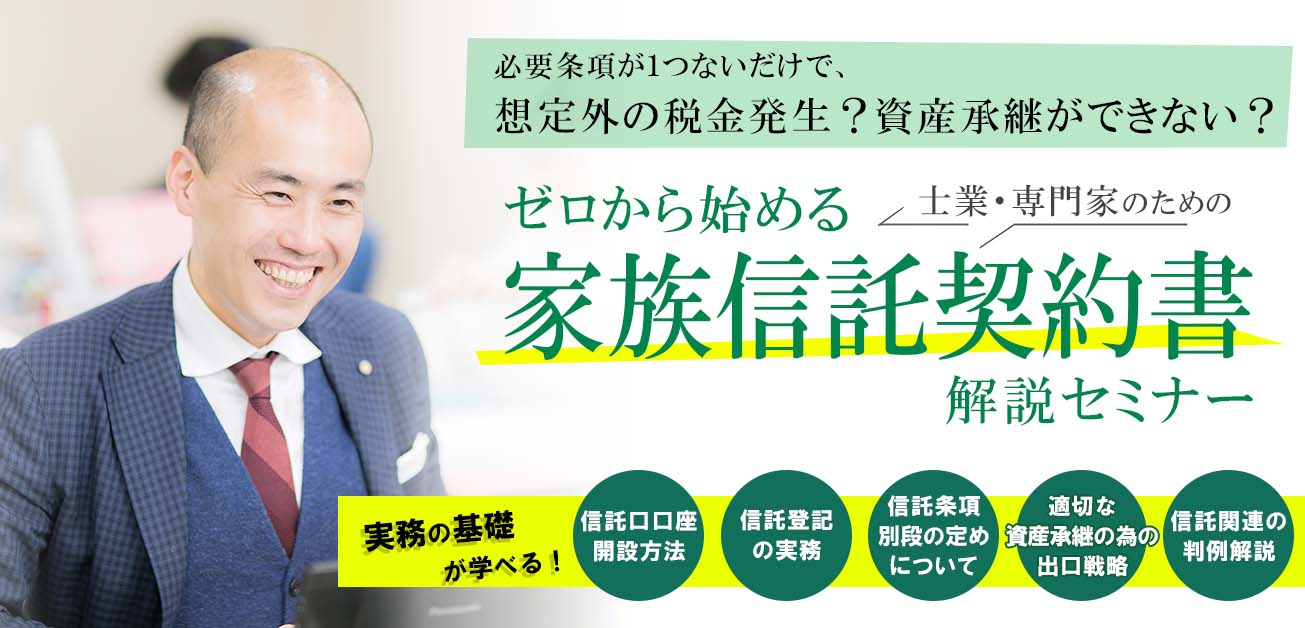
家族信託というのは、士業・専門家にとって遺言や成年後見では対応できなかった範囲をカバーできる「一手法」です。自由度が高い分、お客様のニーズにあわせた対策を設計できます。しかし、一方で、オーダーメイドの契約書というのは経験も必要。そして、制度の歴史も浅く十分な判例もない状況も重なって、なかなかハードルが高く感じる方もいらっしゃるでしょう。
特に、家族信託契約書作成になると士業・専門家の技術が問われます。
もし、間違った信託契約書を作成してしまうと、本来支払う必要がない税金が課税されてしまう、金銭を管理する信託口口座が開設できない、一つの条項がないだけで不動産の売却処分等ができないといったリスクが発生してしまいます。
ここができるのとできないのとでは、士業・専門家にとっては大きな差でもあります。
今回、家族信託組成数400件を超える信託サポート件数TOPクラスのリーガルエステートがその信託契約書の最新情報とともに、作成手法について解説します。
こんな方にオススメです
・これから家族信託をやっていきたいと思っている方
・家族信託契約書を起案する方
・ご自身の顧問先や顧客に家族信託を提案し、他の士業につなぐ方
セミナーでは、家族信託契約の内容と法務、税務の中でも特に重要なことをダイジェストでお伝えします。
【士業・専門家のためのゼロから始める家族信託契約書解説セミナー】
今回のセミナーでは、主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。
- 間違った信託契約書を作成した場合の3つのリスク
- 無駄な税金を払わず、預金口座凍結を防ぐための家族信託契約スキームの徹底解説
- 契約書で要注意!自益信託と他益信託。契約時に想定外の税金がかかることも!?
- 不動産所得がある顧客には要注意!知っておきたい損益通算禁止のリスクと回避方法
- 信託契約後の金銭を管理するための信託口口座の開設手続きの流れ
- 不動産が売却できない!を防ぐための信託契約条項と登記の方法は、ズバリこれ
- 委託者の想いを叶える財産の引き継ぎ方と契約書の定め方とは?
- 信託終了時に想定外の税金が!?信託契約で絶対もれてはいけない契約条項
- 適切な資産承継を考えるためには出口戦略(終わり方)が重要
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]