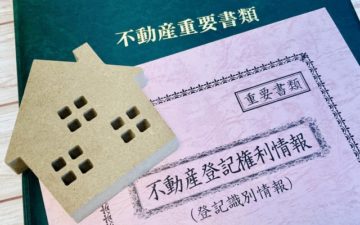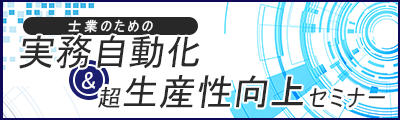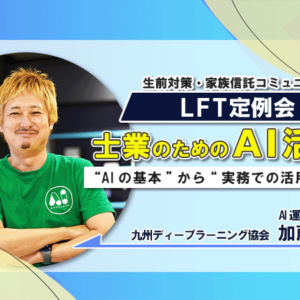最近、東京湾岸のタワーマンションや京都の町家、ニセコの高級リゾートなど、日本の不動産に対する海外投資家からの関心が非常に高まっているのを肌で感じます。円安も後押しとなり、「日本の不動産を買いたい」という問い合わせは、私たちの事務所にも数多く寄せられています。
しかし、いざ日本の不動産を買おうとすると、多くの方が「日本の法律やビジネスの慣習は独特で、手続きが複雑すぎる!」と頭を抱えてしまうのが現実です。
そこで今回は、私たちが日々の実務で培った経験をもとに、「海外に住んでいる方が、どうすれば安全・確実に日本の不動産を買えるのか?」その具体的な手続きと成功の秘訣を、分かりやすく解説していきます。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
- 国籍やビザは関係なし! 外国人でも日本人と全く同じ条件で不動産を買えます。特別な税金もかかりません。
- 専門家選びが成功のカギ。 海外案件の実績が豊富な不動産会社と司法書士をパートナーに選びましょう。
- 日本に来れなくても大丈夫。 事前に「4つの役割の代理人」を決めておけば、手続きはスムーズに進みます。
- 住民票・印鑑証明の代わりは? 「宣誓供述書」という書類があなたの身分証明になります。2024年4月からの新ルールも要チェックです。
- 司法書士を味方につける。 決済代理人に司法書士を指名すれば、お金の管理から登記までワンストップで安心です。
一見、難しそうに感じる国際不動産取引ですが、押さえるべきポイントさえ分かっていれば、決して怖いものではありません。この記事を読めば、ゴールまでの道のりがきっとクリアになるはずです。
目次
1. そもそも、なぜ外国人でも日本の不動産を持てるの?
まずは、渉外登記とはそもそも何?という説明からわかりやすくしていきます。
とてもシンプルな話ですが、日本の法律には「外国人だから不動産を買ってはいけない」という規制が一切ないからです。
国籍やビザの種類、永住権の有無にかかわらず、誰でも日本人と全く同じように、土地や建物のオーナーになることができます。もちろん、買った不動産を売ったり、誰かに贈与したり、相続させたりするのも自由です。
「外国人だと税金が高いのでは?」と心配される方もいますが、不動産を取得するとき(登録免許税・不動産取得税)、持っている間(固定資産税)、売却したとき(譲渡所得税)にかかる税金のルールも、すべて日本人と同じです。
ただし、一つ注意点があります。それは、「不動産を持てば、自動的に日本に住めるビザがもらえるわけではない」ということです。もし日本に長期滞在しながら不動産投資をしたいのであれば、別途「経営・管理ビザ」などを取得する必要があります。この点は誤解されやすいので、私たち専門家も丁寧な説明を心がけている部分です。
2. 取引をスムーズに進めるための「5つの実務ポイント」
ここからは、いよいよ本題です。海外にお住まいの方がストレスなく取引を終えるために、私たちが最も重要だと考えている5つの実務ポイントをご紹介します。
2-1. 外国人対応の実績がある「専門家チーム」を組む
「餅は餅屋」と言いますが、国際不動産取引はまさにこれです。日本には数多くの不動産会社や司法書士がいますが、正直なところ、海外案件に習熟した専門家はまだまだ少ないのが実情です。
単に英語が話せるだけでなく、
・海外からの送金手続き
・後述する「宣誓供述書」の取り扱い
・外国為替及び外国貿易法(外為法)の報告手続き
といった専門的な実務をスムーズにこなせるか、過去の実績で見極めることが不可欠です。
登記手続きの専門家である司法書士は、基本的には、海外にお住まいであっても買主側が主導して選ぶことができます。 売り主指定の司法書士条項が売買契約書にあったとしても、担当する司法書士が国際案件に不慣れであれば、司法書士は買主指定で交渉すべきです。ここはぜひ、こだわっていただきたい重要なポイントです。
2-2. 契約書は「和英併記」で認識のズレを防ぐ
売買契約書や重要事項説明書は、日本の法律に基づき日本語で作成されるのが原則です。しかし、内容を正確に理解できないままサインするのは非常に危険ですよね。
後になって「そんな話は聞いていない!」というトラブルを避けるためにも、契約書の各条項に英語の翻訳を併記してもらうか、別紙で翻訳を用意してもらいましょう。これは、私たち司法書士が登記手続きで使う「委任状」などでも同じです。この一手間が、将来の大きな安心につながります。
2-3. 日本に来なくてもOK!「4つの代理人」を先に決めておく
海外にいながら日本の不動産取引を完結させるための最大の鍵、それが「4つの役割を持つ代理人(キーマン)」をあらかじめ決めておくことです。この4つのポジションを早期に固めておくことで、海外にお住まいの依頼者が日本に来なくても、手続きは驚くほどスムーズに進みます。
1.売買契約代理人
依頼者の代わりに、重要事項説明を受け、売買契約書にサイン・押印をする人です。不動産会社の担当者や、信頼できる日本の知人などが候補になります。
2.残代金決済代理人(推奨:司法書士)
海外から送金された購入代金を預かり、売主への支払いや登記申請を仕切る「司令塔」です。私たち司法書士がこの役割を担うことで、お金の支払いと権利の登記を同時に、安全に実行できます。 為替レートの変動で送金額に過不足が出た場合の調整など、お金に関する複雑な管理も一括してお任せいただけます。
3.納税管理人 (推奨:不動産管理会社、日本在住の知人)
不動産を買った後にかかる税金(不動産取得税や固定資産税など)の手続きを、依頼者である外国人に代わって行う人です。税務署からの通知を受け取ったり、納税を代行したりする重要な役割を担います。
4.国内連絡先(2024年の法改正で必須に!推奨:不動産管理会社、確定申告を行う税理士、日本在住の知人 )
2024年4月から、日本に住所がない所有者は、日本国内の連絡先を登記することが義務付けられました。これは登記簿に載る公式な情報です。司法書士や税理士などを指定しておけば、行政や近隣住民からの連絡にも迅速に対応でき安心です。
【実務の裏ワザ】
上記の③納税管理人と④国内連絡先は、同じ専門家に兼任してもらうと、連絡窓口が一つにまとまり、書類管理や対応が格段に効率的になるのでおすすめです。
2-4. 住民票の代わりに「宣誓供述書+写真付き身分証」を用意する
日本在住者であれば当たり前に取得できる住民票や印鑑証明書。海外にお住まいの外国人は、これらを用意できません。そこで登場するのが「宣誓供述書(Affidavit)」です。
これは、外国人の氏名や現住所が間違いないことを、外国人の国の公証人や在日大使館・領事館で証明してもらう書類です。これにパスポートのコピーと、住所が記載された写真付きの公的な身分証明書(国際運転免許証など)をセットにすれば、住民票などの代わりとして登記申請に使えます。
宣誓供述書には有効期限がないので、日本へ物件を探しに来る前に取得しておくと、その後の手続きが非常にスムーズです。
2-5. なぜ決済代理人に「司法書士」を指名すべきなのか?
先ほども少し触れましたが、なぜ私たちが決済代理人として司法書士を強くおすすめするのか。それは、買主の大切な資産と権利を、取引の最終局面で完璧に守り抜くためです。
司法書士が決済代理人となれば、
海外からの着金確認 → 売主への代金支払い → 法務局への所有権移転登記申請
という一連の流れを、すべて一人の専門家が責任を持ってワンストップで実行します。
送金の遅れや書類の不備で決済が直前に延期になる、といった最悪の事態を未然に防ぎ、安全確実なゴールへと導きます。手数料はかかりますが、その費用に見合うだけの絶大な安心感を得られるはずです。
3. 【完全ガイド】海外在住者が購入するまでの11ステップ
では、具体的にどんな流れで手続きが進んでいくのか、11のステップで見ていきましょう。
1.物件探し:ネットなどを活用し、不動産会社へ問い合わせ。
2.来日前の準備:宣誓供述書などを取得。代理人候補と打ち合わせ。
3.現地内見と買付:物件を実際に確認し、「買付証明書」を提出。
4.資金計画:購入代金の支払い方法(現金/ローン)と送金計画を確定。
5.重要事項説明:不動産会社から物件に関する詳細な説明を受ける。
6.資金の事前送金:決済代理人(司法書士)の口座へ購入資金を送金。
7.売買契約:売買契約代理人が契約書に署名し、手付金を支払う。
8.登記書類の確認:司法書士がすべての書類をチェックし、本人確認を行う。
9.決済・登記申請:司法書士が権利関係に問題ないことを最終確認し、送金と登記申請を同時に実行。
10.外為法報告:取得日から20日以内に、日本銀行へ「不動産を取得した」旨を報告。
11.権利証の受領:登記完了後、法務局から発行される「登記識別情報(従来の権利証)」を受け取り、厳重に保管。
この中で特に時間がかかりがちなのが、(2)書類準備と(8)本人確認です。国際郵便と海外送金の遅れなども考慮し、決済予定日の最低でも1ヶ月半前には準備をスタートするくらいのスケジュール感が理想です。
4. 不動産は「買って終わり」じゃない!取得後の税金とコスト
無事に物件の引き渡しが終わっても、それで終わりではありません。むしろ、所有してからが本当のスタートです。
不動産取得税:購入後、半年~1年ほどで納税通知が届きます。
固定資産税:毎年1月1日時点の所有者に課税され、毎年納税通知が届きます。
所得税:物件を貸して家賃収入を得たり、将来売却して利益が出たりした場合に申告・納税が必要です。
これらの税金手続きは、先ほどご説明した「納税管理人」を通じて行います。納税通知がどこに送られ、誰が、いつまでに支払うのか、あらかじめ決めておくことが非常に重要です。
また、マンションの場合は、毎月の管理費・修繕積立金の支払いも忘れてはいけません。支払いが滞ると、最悪の場合、競売にかけられてしまうリスクもありますので、口座振替の設定などを忘れずに行いましょう。
5.まとめ
今回は、海外にお住まいの外国人が日本の不動産を購入する際の実務手続きについて、私たちの視点から解説しました。
- 国籍やビザは関係なし! 外国人でも日本人と全く同じ条件で不動産を買えます。特別な税金もかかりません。
- 専門家選びが成功のカギ。 海外案件の実績が豊富な不動産会社と司法書士をパートナーに選びましょう。
- 日本に来れなくても大丈夫。 事前に「4つの役割の代理人」を決めておけば、手続きはスムーズに進みます。
- 住民票・印鑑証明の代わりは? 「宣誓供述書」という書類があなたの身分証明になります。2024年4月からの新ルールも要チェックです。
- 司法書士を味方につける。 決済代理人に司法書士を指名すれば、お金の管理から登記までワンストップで安心です。
どんな不動産取引にも言えますが、特に国をまたぐ取引の要諦は、「工程表の事前設計」に尽きます。各ステップの担当者、期限、必要書類をリストアップし、時差や海外送金のルールまで考慮してタスクを割り振る。この設計図さえしっかり描けていれば、ほとんどのリスクは事前に回避できます。
特に、海外からの送金、複雑な本人確認、そして代金の支払いと登記申請という最終局面を、一つのミスもなく完璧につなぎ合わせる。これこそが、私たち司法書士の専門性であり、腕の見せどころです。
この記事が、国際不動産取引に携わる専門家の方々の皆様にとって、少しでも道しるべとなれば、これほど嬉しいことはありません。
【無料オンライン】外国人・海外居住者取引特有の決済と登記の実務ポイント

外国人・海外居住者との不動産取引が急増する中、多くの不動産会社が外国人の依頼を受けることに課題を抱えています。特に注目すべきは、海外在住者との売買に特有の実務上の様々な違い、外国送金に関する対応の問題、登記実務における外国語文書の取扱いです。
実際の現場では、海外居住者との必要書類のやり取り、外国人特有の本人確認手続き、さらには事後的な財務省への報告まで、国内取引とは異なる多岐にわたる実務知識が必要とされています。また、外国人取引実務に精通した不動産業者や司法書士が少ない中、2024年4月の外国人登記に関する改正など、現場では常に最新の知識が求められています。
本セミナーでは、外国人・海外居住者との取引における実務フローを、決済・登記から事後手続きまで、体系的に解説します。不動産実務において押さえるべき国際取引の要点と、スムーズな取引進行のためのノウハウを包括的に理解する機会です。国際化が進む不動産市場において、他社との差別化を図りたい不動産会社の皆様にとって、このセミナーは実務の質を高め、新たな取引機会の創出につながる実践的な内容となっています。
セミナー内容
- 外国人・海外居住者取引特有の日本人売買との違いとポイント
- 国際送金と決済の実務的な対応
- 外国人・海外居住者取引における登記実務と事後対応
詳細は下記のリンクをご覧ください。
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]