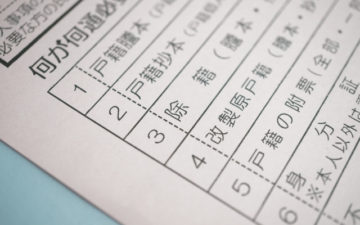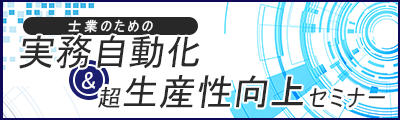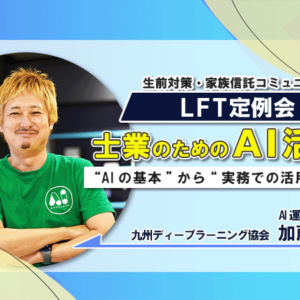2026年4月1日、所有権登記名義人の「住所等の変更登記」が、ついに義務化されます。2024年4月の相続登記義務化に続くこの動きは、所有者不明土地問題という長年の課題に対する国の本気度を示すものです。
この法改正は、我々司法書士・行政書士の実務に、間違いなく大きな影響を与えます。もはや「知らなかった」では済まされないこの新制度に対し、我々はお客様へ何を伝え、どう導くべきなのでしょうか。この記事では、この住所変更登記義務化というテーマについて、その概要と実務家目線での対応策を解説します。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
- 義務化の開始と具体的な期限: 2026年4月1日以降、住所等の変更があった日から2年以内の登記申請が義務となります。施行日前の未登記案件にも適用され、その場合は施行日から2年間の猶予期間が設けられます。
- 過料のリスクと回避策: 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。しかし、登記官による催告に応じて申請すれば過料は科されません。
- 職権登記制度の活用: 個人の「検索用情報」や法人の「会社法人等番号」を事前に申し出ることで、登記官が職権で変更登記を行う制度が新設されます。この場合、登録免許税は非課税となります。
- 実務上の手続きと必要書類: 登記申請における必要書類、特に住所の変遷を証明する「戸籍の附票」等の要否判断が重要となります。登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
- 相続登記義務化との連携: 既に義務化されている相続登記と住所変更登記は、セットで捉え、遺産承継業務等において一体的に対応する必要があります。
目次
1.不動産の住所変更登記とは?義務化の歴史的背景と専門家の責務
「所有権登記名義人住所変更登記」———。私たち実務家にとっては馴染み深いこの登記ですが、これまではあくまで任意の申請でした。そのため、お客様が転居やご結婚をされても、登記簿上の住所や氏が古いまま放置されている、というケースは決して珍しくありませんでした。先生方も、実務の中で一度はそういった場面に遭遇されたことがあるのではないでしょうか。
しかし、その一つ一つの「放置」が積み重なり、「所有者不明土地問題」という、日本社会全体の大きな課題を生み出す一因となってしまいました。登記簿を見ても本当の所有者にたどり着けない。これでは、円滑な経済活動など望むべくもありません。相続業務においても、被相続人の登記簿上の住所と最終住所が異なれば、権利関係を証明するための労力は計り知れないものになります。
こうした背景から、国はついに不動産登記法の大改正に踏み切りました。今回の住所変更登記義務化は、先行する相続登記義務化と対をなす、いわば所有者情報を常に最新に保つための「両輪」です。我々専門家は、この法改正の深い意図を汲み取り、お客様の権利を守り、社会の期待に応えていくという、重くもやりがいのある責務を負っているのです。
2.【徹底解説】2026年4月1日施行・住所変更登記義務化の新ルール
さて、ここからは2026年4月1日からスタートする新制度の具体的な内容について、実務で本当に役立つレベルまで踏み込んで解説していきます。お客様への説明や案件対応の勘所を、ぜひ掴んでいただければと思います。
2-1. 登記申請義務の内容と期限の正確な理解
改正不動産登記法が我々に課すのは、所有権の登記名義人の住所・氏名に変更があった日から「2年以内」に、その変更登記を申請する義務です(改正不動産登記法第76条の5)。例えば、2026年7月15日にお客様が転居された場合、その申請期限は2028年7月14日となります。このルールは、個人・法人を問わず、すべての所有者に適用されるという点がポイントです。
【実務ポイント①】施行日前の住所変更への遡及適用と経過措置
ここで特に注意したいのが、2026年4月1日の施行日より前に生じた住所変更も、未登記であれば義務の対象になるという点です。
これは、過去の住所変更を放置している多くのお客様にとって、非常にインパクトの大きい話ではないでしょうか。 幸い、これには経過措置が用意されています。施行日前の変更については、施行日である2026年4月1日から2年間、つまり2028年3月31日までに登記をすればセーフ、とされています。この2年間の猶予期間は、我々が顧客に働きかける上で、極めて重要な意味を持つ期間と言えるでしょう。

【実務ポイント②】義務違反に対する「過料」というペナルティ
もし、正当な理由なくこの義務を怠った場合、どうなるのか。法律は「5万円以下の過料」というペナルティを用意しています(改正不動産登記法第164条第2項)。過料は、前科が付く刑罰(罰金)とは異なりますが、お客様にとっては紛れもない金銭的負担です。
このリスクについては、きちんと正確に伝えておくのが専門家としての姿勢だと考えます。
2-2. 【新設】登記官の職権による変更登記制度
今回の法改正で、もう一つ注目すべきは、登記官が職権で住所変更登記を行うという、画期的な制度が導入される点です。これは、私たちの実務、特にお客様への提案の幅を大きく広げる可能性を秘めています。

■個人の場合:検索用情報の申出
個人のお客様は、法務局に自らの氏名、住所、生年月日などを「検索用情報」として申し出ることができます。これを一度行っておけば、法務局が住基ネットを通じて住所変更をキャッチし、所有者本人の同意を得た上で、自動的に登記簿を書き換えてくれるのです。
この制度の魅力は、何と言ってもその手軽さと経済性でしょう。将来の住所変更のたびに申請する手間が省け、しかも職権登記にかかる登録免許税(不動産1個につき1,000円)が非課税になるのですから、提案しない手はありません。
ただし、登記実行には「本人の同意」というワンクッションがある点は、念のため申し添えておくと親切です。
■法人の場合:会社法人等番号の申出
法人の場合はさらにスムーズです。不動産登記に「会社法人等番号」を紐づけておけば、商業登記で本店移転などの変更登記を行うだけで、不動産登記も自動的に更新されます。
個人の場合と違い、法人の同意は不要です。商業登記さえ適切に行っていれば、あとは法務局が職権で進めてくれます。こちらも登録免許税は非課税。法人顧客には、今すぐにでも申出を推奨すべき、非常にメリットの大きい制度だと言えます。
【実務ポイント③】職権登記の対象外となるケース:海外居住者・会社法人等番号のない法人
ここで極めて重要な注意点があります。この便利な職権登記制度は、海外に居住する個人や、会社法人等番号を持たない法人(外国法人や一部の特殊法人など)には適用されません。これらの個人・法人については、日本の住基ネットや商業・法人登記システムとの情報連携ができないため、登記官が住所や名称の変更を公的に把握することが不可能です。
そのため、海外に居住されているお客様や、会社法人等番号のない法人顧客が住所や名称を変更した場合は、職権登記に頼ることはできず、必ず所有者自身が法務局に対して2年以内に住所変更登記の申請を行う必要があります。

国内居住者と比べて手続きが忘れられがちになるため、我々専門家は、該当する顧客に対して、この点を特に強調してアナウンスし、期限内に確実に手続きを済ませるよう導く責務があります。
2-3. 義務違反の把握から過料までの実務フロー
では、法務局は一体どうやって義務違反を見つけるのでしょうか。まさか、全国の登記名義人を片っ端から調査するわけではありません。運用としては、他の登記申請があった際などに、「附随的」に把握する形が想定されています。
【義務違反が把握される典型例】
・他の登記申請時: 売買や表示変更登記の申請書に書かれた現住所と、登記簿上の住所が違う、という最も分かりやすいケースです。
・職権登記のための照会時: 住基ネットで住所変更が判明したのに、法務局からの案内に応答しない、といったケースも考えられます。
義務違反を見つけても、登記官はすぐには過料の手続きに進みません。 まず、登記名義人に対し、「期間を定めて登記してください」という「催告」を行います。この催告期間内にきちんと申請すれば、たとえ2年の期限を過ぎていても、お咎めなし。これは、実務上、非常に重要な救済措置です。
しかし、この催告を無視し、かつ後述する「正当な理由」も示せないとなると、いよいよ裁判所への通知、そして過料の決定という流れになります。
2-4. 過料を免れる「正当な理由」とは
法律は、やむを得ない事情がある場合にまで過料を課すような、無慈悲なことはしません。「正当な理由」があれば、義務違反は問われないのです。
・職権登記制度の未了: ちゃんと申出はしたのに、登記官の手続きが追いついていない場合。
・行政による住所変更: 市町村合併など、自分の意思とは関係ない住所変更。
・重篤な疾病等: 本人が重病で、とても手続きどころではない状況。
・DV被害等による避難: 住所を明らかにすることで身に危険が及ぶ可能性がある場合。
・経済的困窮: 生活保護を受けているなど、登記費用を払うのが客観的に難しい場合。
これらの理由は、法務局から催告を受けたタイミングで、自ら主張・立証するのが基本です。診断書や公的な証明書など、客観的な証拠を添えて丁寧に説明する必要があります。こうした状況にある顧客を、法的な知識と具体的な手続きで支えることこそ、我々専門家の腕の見せ所と言えるでしょう。
3.住所変更登記は相続登記義務化とセットで考える
これまで見てきたように、住所変更登記義務化は、相続登記義務化とセットで考えるべきものです。「相続を知ってから3年」「住所変更から2年」。この2つの期限が、これからの不動産登記実務の基本リズムとなります。
私たちが相続の相談を受けた際には、必ず以下の視点を持つべきです。
・被相続人の住所変更登記漏れの有無: 登記事項証明書と被相続人の最終住所を照合することは、もはや必須の業務フローです。
・相続人の未来へのアドバイス: 新たに名義人となる相続人に対し、「これから転居されたら、2年以内に登記が必要となります、そのためメールアドレスを法務局に届けておくとよいですよ」と一言添える。この小さな心遣いが、未来のトラブルを防ぎ、専門家としての信頼を深めることに繋がります。
相続と住所変更。この2つの義務化は、所在不明土地問題を解決するためのものです。両者の制度を理解し、顧客にアドバイスが今後必要となってきます。
4.まとめ
ここまで、2026年4月から始まる住所変更登記義務化について、実務的な観点から考察してきました。最後に、本稿の要点を改めて確認しましょう。
- 義務化の開始と具体的な期限: 2026年4月1日以降、住所等の変更があった日から2年以内の登記申請が義務となります。施行日前の未登記案件にも適用され、その場合は施行日から2年間の猶予期間が設けられます。
- 過料のリスクと回避策: 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。しかし、登記官による催告に応じて申請すれば過料は科されません。
- 職権登記制度の活用: 個人の「検索用情報」や法人の「会社法人等番号」を事前に申し出ることで、登記官が職権で変更登記を行う制度が新設されます。この場合、登録免許税は非課税となります。
- 実務上の手続きと必要書類: 登記申請における必要書類、特に住所の変遷を証明する「戸籍の附票」等の要否判断が重要となります。登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
- 相続登記義務化との連携: 既に義務化されている相続登記と住所変更登記は、セットで捉え、遺産承継業務等において一体的に対応する必要があります。
今回の法改正は、私たち専門家にとって、新たなビジネスチャンスであると同時に、お客様へのアドバイスが必要です。この記事が、明日からの先生方の実務において、何かしらのヒントとなれば、幸いです。
「法改正はビジネスチャンス」で終わらせない。具体的な”集客”と”受任力”を磨くには?
今回の法改正が、私たち専門家にとって新たな責務とビジネスチャンスをもたらすものであることは、先生方も強く感じていらっしゃることと存じます。住所変更登記や相続登記の相談を入口に、お客様の抱えるより本質的な課題、すなわち「未来への資産承継」にどう寄り添っていくか。その手腕が、今後ますます問われることになるでしょう。
・法改正をきっかけに、どうやってお客様にアプローチすればいいのか?
・手続きの話だけでなく、もっと踏み込んだ生前対策の提案がしたいが、どう切り出せば?
・高付加価値な業務で、事務所の経営基盤を盤石にしたい
もし先生が、こうした課題意識や目標をお持ちでしたら、私たちが開催する無料セミナーが、その突破口となるかもしれません。
セミナーでは下記の内容を伝えています。
- 相続・家族信託のマーケットの状況
- 士業・専門家業の時代の流れと高収益生前対策案件受任の発想方法
- 家族信託、任意後見、遺言など生前対策提案の活用方法
- 生前対策・家族信託コンサル業務における商品設計のコツとは
- 生前対策・家族信託相談からの不動産提案のポイント
- 価格競争に陥らず、安定的に相談者を増やすコツ
- 生前対策から相続手続きまでのLTV(生涯顧客最大価値)を高めるためのポイント
- 選ばれている士業・専門家のポジショニングの秘訣
- 提案型業務への移行の7つのステップとは
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]