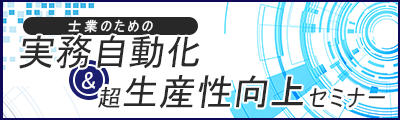多くの士業・専門家の事務所でも最近、こんなご相談、ありませんでしたか?
「父は長年日本で暮らしていたアメリカ人なのですが、相続手続きはどうすれば…」
「相続人の一人がテキサス州に住んでいて、遺産分割協議に応じてくれません…」
「被相続人の出生証明書は取れたのですが、これで相続人全員だと証明できるのでしょうか…」
渉外相続、特に米国籍の方が絡む案件は、準拠法の判断でまず立ち止まります。州ごとに法が異なる「法域不統一国」であるため、どの州のルールを辿ればいいのか。ようやく日本法が適用できると分かっても、今度は日本の「戸籍」にあたる証明書が存在しない壁にぶつかります。
相続人から送られてきた宣誓供述書(Affidavit)を手に、これで登記が通るのかと管轄法務局と何度も協議を重ねる…そんなご経験をお持ちの先生も少なくないはずです。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
- 在日米国人の相続では、実務上、米国州法の分割主義(不動産は所在地法、動産は住所地法)により、日本国内の財産には日本法が適用される。
- 米国内に財産が残存する場合、日本の手続とは別に、原則として現地のプロベート(裁判検認)手続の対象となる。
- 米国籍当事者の相続証明は、戸籍制度がないため、公的な証明書に加え、「他に相続人はいない」旨の宣誓供述書(Affidavit)の作成が不可欠。
- 海外在住相続人が遺産分割協議に参加する場合、印鑑証明書に代わり、現地公証人等が認証した署名証明書(またはそれに準ずる書面)を添付する必要がある。
- 【令和6年4月施行】海外居住の相続人が不動産を取得する場合、新たに「国内連絡先に関する事項」の登記が義務付けられた点に注意が必要。
こうした一筋縄ではいかない在日米国人の相続案件に焦点を当て、明日からの実務に直結する論点を網羅的に解説していきます。
目次
1.渉外相続における準拠法の特定プロセス
渉外相続案件の羅針盤となるのが「準拠法」の特定です。この最初のステップを正確に行うことが、案件全体の成否を左右します。特に被相続人が米国籍の場合、その特定プロセスは多段階の検討を要します。
1-1.大原則:法の適用に関する通則法第36条
まず確認すべきは、我が国の国際私法である「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」)です。通則法第36条は、相続の準拠法について以下のように定めています。
(相続) 第三十六条
相続は、被相続人の本国法による。
条文上は「被相続人の本国法」とシンプルですが、相手国が米国の場合、この「本国法」が何を指すのかが最初の論点となります。
1-2.論点①:米国が「法域不統一国」であることの意味
ご存知の通り、アメリカ合衆国は50の州と連邦区から構成される連邦国家であり、相続に関する法律は各州が独自に定めています。このように、国内で法の内容が地域によって異なる国を、通則法上「法域不統一国」と呼びます。
この場合、どの地域の法を適用すべきかについて、通則法第38条第3項が指針を示しています。
(当事者の本国法) 第三十八条 3
当事者が地域的に法律を異にする国に国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される地域の法律を、そのような規則がないときには当事者に最も密接な関係がある地域の法律を当事者の本国法とする。
この規定に従い、我々は以下のステップで準拠法を絞り込んでいくことになります。
段階1:米国の抵触法のルール(連結指定規則)を確認する
「その国の規則」とは、米国の国際私法(Conflict of Laws)が、渉外相続においてどの州法を適用するよう定めているか、そのルールを指します。
段階2:最も密接な関係がある地域の法を適用する
もし米国内に統一的な連結指定規則が存在しない場合は、「被相続人に最も密接な関係がある地域」の法、すなわち、通常は被相続人の最後の住所(Domicile)があった州の法律を適用することになります。
1-3. 論点②:分割主義(Scission System)と反致(Renvoi)の成立
ここで、段階1の「米国の抵触法のルール」が重要になります。米国の多くの州では、相続の準拠法について「分割主義(Scission System)」という考え方を採用しています。これは、相続財産の種類によって適用される法律を分けるアプローチです。
・不動産(Immovables): その不動産の所在地法(lex rei sitae)を適用する。
・動産(Movables): 被相続人の最後の住所地法(lex domicilii)を適用する。
例えば…この分割主義を、在日米国人のケースに当てはめて、被相続人が長年日本に居住し、その住所(Domicile)が日本にあったとすると
・日本国内の不動産について → 不動産の所在地は「日本」であるため、米国の抵触法は日本法を準拠法として指定します。
・日本国内の動産(預貯金等)について → 被相続人の住所地は「日本」であるため、米国の抵觸法は日本法を準拠法として指定します。
このように、日本の国際私法(通則法)が被相続人の本国法(米国法)を準拠法として指定したところ、その本国法(米国の抵触法)が再び日本法を指定し返してくる現象を「反致(Renvoi)」と呼びます。通則法第41条本文は、この反致の成立を認めています。
結果として、在日米国人が日本国内に残した不動産・動産の相続については、日本の民法が準拠法として適用されるという結論に至ります。これが、実務上の出発点となります。
2.米国の相続手続「プロベート」の理解
2-1.プロベート(Probate)とは何か
プロベートとは、被相続人の死亡後、その遺産を管理・清算し、最終的に相続人や受遺者に分配するための一連の裁判手続きを指します。コモン・ロー(英米法)の国に共通する制度であり、その主な特徴は以下の通りです。
・裁判所の監督: 全ての手続きは、管轄の裁判所(Probate Court)の監督下で行われます。
・遺産人格代表者(Personal Representative)の選任: 裁判所は、遺言で指名された者(Executor)または法定の遺産管理人(Administrator)を遺産人格代表者として選任します。
・財産の収集と債務の弁済: 選任された代表者は、被相続人の財産を収集・管理し、債権者への公告・弁済、税金の申告・納付などを行います。
・遺産の分配: 全ての債務・経費を清算した後、残った財産を遺言または州の法定相続分に従って相続人に分配します。
日本の相続が、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を基本とする「当事者主義」であるのに対し、プロベートは裁判所が厳格に管理する「清算型」の手続きであり、根本的に思想が異なります。
2-2.日本国内の財産とプロベートの関係
前章で解説した通り、在日米国人の日本国内財産には日本法が適用されます。したがって、これらの財産は米国のプロベート手続の対象外です。
日本の銀行預金や不動産については、米国の裁判所の許可を得ることなく、日本の民法の規定に従って、遺産分割協議や法定相続による手続きを進めることが可能です。この点を依頼人に明確に説明することが重要です。
2-3. 米国内に財産が残存する場合の実務対応
問題は、被相続人が米国内に銀行口座、株式、不動産などを残している場合です。これらの財産は、現地の州法に基づき、原則としてプロベートの対象となります。
この場合、相続手続きは日米で二つに分かれます。
・日本での手続: 日本国内の財産について、司法書士が遺産分割協議書の作成や相続登記を支援する。
・米国での手続: 米国内の財産について、現地の弁護士(Attorney)に依頼し、プロベート手続きを進めてもらう。
専門家は、プロベート手続きを直接行うことはできませんが、依頼人のために信頼できる現地の弁護士を紹介したり、連携して情報共有を図ったりする役割が期待されます。
要注意:プロベートを回避する生前対策
プロベートは、一般的に多大な時間(1年~数年)と費用(弁護士費用、裁判所費用等)を要します。そのため、米国では生前にプロベートを回避するための対策を講じることが一般的です。
・リビング・トラスト(Living Trust): 生前に信託を設定し、財産をトラスト名義に移しておくことで、相続財産から除外し、プロベートを回避します。
・ジョイント・テナンシー(Joint Tenancy with Right of Survivorship): 不動産等を複数の所有者で共有し、一人が死亡するとその持分が自動的に他の生存所有者に帰属する形態。
これらの知識は、生前の相続対策相談に応じる際に非常に有用です。
3.相続登記における登記原因証明情報(代替書面)の作成実務
日本の不動産登記実務は、個人の同一性や身分関係の証明を、市区町村が発行する戸籍謄本・住民票・印鑑証明書に大きく依存しています。しかし、米国にはこれらの制度が存在しません。
そのため、登記申請の添付情報として、これらの公文書が持つ「証明機能」を代替する書面を、我々専門家が主体となって作成・収集する必要があります。
3-1.被相続人の死亡を証する情報
これは比較的シンプルです。以下のいずれかの書面を取得します。
・Consular Report of Death of a U.S. Citizen Abroad(国外での米国市民の死亡報告書): 在日米国大使館または領事館で発行されます。被相続人の氏名、生年月日、死亡日、死亡場所等が記載されており、死亡の事実を証明する上で最も確実な書面の一つです。
・死亡届記載事項証明書: 日本国内で死亡し、市区町村役場に死亡届を提出している場合、その役場で発行される証明書も利用できます。
3-2. 相続人の範囲を証明する情報(最重要論点)
ここが最大のポイントです。日本の戸籍謄本であれば、被相続人の出生から死亡までの連続した記録により、「相続人はこれで全員であり、他に相続人はいない」ことを証明できます。
しかし、米国籍当事者の場合、以下の公的証明書を組み合わせても、この「他の相続人の不存在証明」ができません。
・Birth Certificate(出生証明書)
・Marriage Certificate(婚姻証明書)
・Death Certificate(死亡証明書)
これらはあくまで、個々の出生、婚姻、死亡という事実を証明するに過ぎません。そこで、登記実務ではこれらの公的証明書を補完するために、相続人自身による証明として「宣誓供述書(Affidavit)」を活用します。
宣誓供述書(Affidavit)
宣誓供述書は、相続人の一人が、または相続人全員が、公証人(Notary Public)等の権限ある者の面前で、記載内容が真実であることを宣誓して作成する書面です。登記原因証明情報の中核を担うこの書面には、以下の事項を盛り込む必要があります。
・宣誓供述人の特定: 氏名、住所、生年月日、国籍等
・被相続人の特定: 氏名、最後の住所、死亡日、死亡場所等
・相続関係の陳述:
被相続人の出生から死亡までの婚姻歴、離婚歴、子の出生等
被相続人の両親、兄弟姉妹(法定相続人調査に必要な範囲)
相続人が誰であるかの明示
「上記の者以外に、被相続人の相続人となる者は一人もいない」という確定的な宣誓文言
・相続財産(対象不動産)の表示及び遺産分割協議の内容等
・宣誓日、署名
・公証人による認証文言
【認証の方法】
認証は、以下のいずれかの方法で行います。
・在日米国大使館・領事館の領事による認証: 日本在住の米国籍相続人が利用できます。
・米国現地の公証人(Notary Public)による認証:米国在住の相続人が利用します。
3-3.遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書の代替書類
日本法が準拠法であるため、遺産分割は日本の方式、すなわち遺産分割協議で行い、遺産分割協議書を作成します。ここでの論点は、海外在住の相続人の署名と、それを証明する添付書面です。
日本の相続人が実印を押し印鑑証明書を添付するのと同様に、米国の相続人には、署名が本人のものであることを証明する書面が求められます。
・署名証明書(在米日本大使館・領事館発行): これが最も確実な方法です。現地の日本領事が本人の面前で署名させ、その署名が本人のものであることを証明してくれます。日本の印鑑証明書とほぼ同等の証明力を持ちます。
・宣誓供述書形式での代替: 遺産分割協議書の内容が真実である旨を宣誓供述書にし、現地公証人の認証(+アポスティーユ)を受ける方法もあります。この宣誓供述書が、署名証明と住所証明を兼ねることも多いです。
3-4. 日本語訳文の添付
言うまでもありませんが、死亡証明書、宣誓供述書など、外国語で作成された全ての書面には、翻訳者を明記した日本語訳文を添付する必要があります。
4.【2024年法改正】海外居住者の登記事項とその他の留意点
最後に、近年の法改正と、登記実務以外の関連知識について触れておきます。
4-1. 国内連絡先事項の登記義務化
2024年(令和6年)4月1日に施行された改正不動産登記法により、登記名義人となる者が海外居住者(日本に住所を有しない個人・法人)である場合、国内連絡先に関する事項が登記事項となりました。
・登記事項: 国内に住所を有する者など、連絡先となる者の氏名・名称、住所等
・添付情報: 国内連絡先となる者の承諾を証する情報(個人の場合は印鑑証明書付きの承諾書、法人の場合は会社法人等番号など)
相続登記においても、相続人の一人が米国在住者である場合、この規定が適用されます。申請時に、国内に住む親族や依頼を受けた司法書士自身を国内連絡先とするなどの対応が必要となります。申請漏れがないよう、厳重な注意が必要です。
4-2. 登記名義人の氏名の表記(ローマ字氏名の併記)
外国人の方が登記名義人となる場合、氏名(片仮名表記)とあわせて、そのローマ字氏名を申し出ることで登記簿に記録することができます。その際の添付情報は、在留資格によって異なります。
・中長期在留者: ローマ字氏名が記載された住民票の写し
・短期滞在者・海外居住者: 有効なパスポートの写し(原本と相違ない旨の記載と署名または記名押印が必要)
5.まとめ
- 在日米国人の相続では、実務上、米国州法の分割主義(不動産は所在地法、動産は住所地法)により、日本国内の財産には日本法が適用される。
- 米国内に財産が残存する場合、日本の手続きとは別に、原則として現地のプロベート(裁判検認)手続の対象となる。
- 米国籍当事者の相続証明は、戸籍制度がないため、公的な証明書に加え、「他に相続人はいない」旨の宣誓供述書(Affidavit)の作成が不可欠。
- 海外在住相続人が遺産分割協議に参加する場合、印鑑証明書に代わり、現地公証人等が認証した署名証明書(またはそれに準ずる書面)を添付する必要がある。
- 【令和6年4月施行】海外居住の相続人が不動産を取得する場合、新たに「国内連絡先に関する事項」の登記が義務付けられた点に注意が必要。
在日米国人の相続案件は、通則法による準拠法の判断から始まり、米国特有のプロベート制度への理解、そして日本の戸籍制度を前提としない代替書面の作成まで、実に多岐にわたる知識とスキルが要求されます。画一的な処理が通用しない、専門家の対応力が求められる分野と言えるでしょう。
国際化が進む現代において、こうした案件は今後ますます増加していくことが予想されます。法改正や国際情勢の動向を常にキャッチアップし、自らの知識をアップデートし続けること。そして、一つ一つの事案に誠実に向き合い、依頼人の権利を擁護するために最善を尽くすこと。複雑な渉外相続案件においてこそ、我々専門家の真価が問われていきそうです。
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]