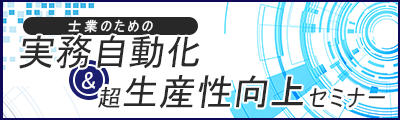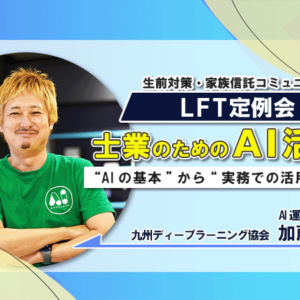近年、国際結婚や海外居住者の増加に伴い、外国籍の被相続人や相続人が関与する国際相続の案件が増加しています。
相続人や被相続人が全て日本人である場合の相続手続きは難なく行える先生方でも、外国人が関係している相続となると、必要書類等を確認し直す先生もいらっしゃることかと思います。
本記事では、司法書士・行政書士の先生方向けに、実務で使う知識が整理できるように、外国人の相続手続きと相続登記の実務上のポイントを基礎から解説します。
今回の記事のポイントは下記の通りです。
- 日本の相続制度は、原則として相続統一主義および本国法主義を採用しており、外国人の相続手続きも同様に取り扱われる
- 外国人が日本または海外で作成した遺言については、遺言作成時の国籍地や住所地など、その国の法律に適合していれば有効とされる。ただし、遺言の成立および効力については、本国法によって判断される
- 相続人や被相続人の国籍に関わらず、日本国内にある不動産を相続する場合には、日本の法制度に基づいた相続登記手続きが必要となる
- 日本の不動産の相続登記には、戸籍、住民票、印鑑証明書の提出が求められるが、これらの制度が存在しない国の場合には、「死亡証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」「宣誓供述書」などの代替書類とその翻訳文を準備する必要がある
- 日本国内の財産を相続する場合、相続税が課税される。原則として、国内外のすべての財産が相続税の課税対象となるが、相続人および被相続人がともに日本国内に住所を有していないなど、一定の要件を満たす場合には、国内財産のみが相続税の対象となる
目次
1. 国際相続とは
国際相続とは、以下のいずれかのケースに該当する相続を指します。
・被相続人が外国籍である場合
・相続人が外国籍または海外在住である場合
・相続財産が国外に存在する場合
国際相続では、適用すべき法律の選定が重要であり、通則法第36条に基づき、原則として被相続人の本国法が適用されます。
1-1. 適用される法の原則
日本の相続法では、以下の原則が適用されます。
・相続統一主義:全財産に一つの法律を適用する
・本国法主義:被相続人の国籍国の法律を適用する
・反致:外国の法律に基づき日本法が適用されることもある(通則法第41条)
これらの原則により、どの国の法律を適用するかを判断します。
2. 外国籍の被相続人の相続手続き
2-1.必要書類
外国籍の被相続人の相続手続きを進めるには、以下の書類が求められます。
・被相続人の死亡証明書(本国発行)
・被相続人と相続人の親族関係を証明する書類(出生証明書・婚姻証明書など)
・遺産分割協議書(必要に応じて)
・外国籍相続人のパスポートコピー
・相続財産の証明書(登記簿謄本、不動産評価証明書など)
注意点:日本の戸籍制度がない国では、被相続人の身分関係を証明するために、宣誓供述書を求める場合があります。
2-2. 日本国内の財産がある場合
被相続人が外国籍であっても、日本国内に不動産がある場合は、日本法に基づき相続登記を行います。通則法により、反致が適用される場合、日本の法律で相続手続きが行われることになります。
3. 相続登記の実務
3-1. 必要書類
日本国内の不動産の相続登記では、以下の書類が求められます。
・相続関係を証明する書類(戸籍謄本の代替書類)
・相続人の本人確認書類(パスポート・在留カードなど)
・遺産分割協議書(必要な場合)
・登記申請書
・登録免許税の納付(不動産評価額の0.4%)
外国語の書類について:外国語で作成された証明書類は、日本語翻訳が必要です。翻訳者の資格要件はありませんが、専門家による翻訳が望ましいです。
3-2. 外国籍相続人の印鑑証明書の代替
印鑑証明制度のない国の相続人には、次の代替書類を取得します。
・サイン証明書:現地公証人が署名の真正性を証明
・宣誓供述書:相続関係を証明する書類として活用
注意点:公証書にアポスティーユ(Hague Convention適用国)または領事認証が必要となる場合があります。
4. 国際相続における相続税
4-1. 相続税の課税対象
相続税の課税対象範囲は、被相続人と相続人の住所地によって異なります。
・被相続人または相続人が日本に住所を持つ場合:国内外のすべての財産が課税対象
・被相続人・相続人が共に非居住者の場合:国内財産のみが課税対象
4-2. 相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です。
・外国在住の相続人:代理人を通じて申告する必要がある
・外貨建て財産:相続開始日の為替レート(TTB/TTS)で換算
ここまで国際相続の注意点・要点を記載してきましたが、上記内容について、より踏み込んだ論点については、下記のリンクのブログ記事を参照してください。
5. まとめ
- 日本の相続制度は、原則として相続統一主義および本国法主義を採用しており、外国人の相続手続きも同様に取り扱われる
- 外国人が日本または海外で作成した遺言については、遺言作成時の国籍地や住所地など、その国の法律に適合していれば有効とされる。ただし、遺言の成立および効力については、本国法によって判断される
- 相続人や被相続人の国籍に関わらず、日本国内にある不動産を相続する場合には、日本の法制度に基づいた相続登記手続きが必要となる
- 日本の不動産の相続登記には、戸籍、住民票、印鑑証明書の提出が求められるが、これらの制度が存在しない国の場合には、「死亡証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」「宣誓供述書」などの代替書類とその翻訳文を準備する必要がある
- 日本国内の財産を相続する場合、相続税が課税される。原則として、国内外のすべての財産が相続税の課税対象となるが、相続人および被相続人がともに日本国内に住所を有していないなど、一定の要件を満たす場合には、国内財産のみが相続税の対象となる
司法書士・行政書士として、案件を継続的に受注してくためには、国際相続の基本的な法的枠組みを理解し、適切な手続きをスムーズに案内できることが重要です。
適切な準備と対応を行い、クライアントの円滑な相続手続きをサポートしましょう。
【動画セミナー】国際相続の税務基礎と士業が押さえておくべき留意点

増加する国際相続案件に備える!税理士が解説する実務のすべて
グローバル化の進展に伴い、国際相続の案件は年々増加傾向にあります。海外在住の親族がいる場合や、海外に資産を保有するケースなど、国際相続は今や特殊なものではなく、士業専門家として日常的に直面する課題となっています。特に、各国の相続税制の違いや二重課税の問題、国際間での相続手続きなど、国内相続以上に複雑な対応が求められます。
しかし、国際相続の実務では、準拠法の決定から相続税の納税義務判定まで、多岐にわたる専門知識が必要です。各国の法制度や税務上の取り扱いが異なるため、誤った判断は予期せぬ税負担やトラブルを招く可能性があります。
本セミナーでは、国際相続の実務に精通している中山史子氏をお迎えし、相続税の無制限納税義務者と制限納税義務者の判定から国際間での二重課税の調整方法まで、専門家として押さえるべき重要なポイントを体系的に解説していただきました。中山氏は、相続税申告業務から事業承継、国際間相続・贈与といったコンサルティング業務まで幅広く従事されており、豊富な実務経験に基づいた実践的な知識を提供していただけます。
国際相続の生前対策から相続発生後の具体的な実務対応まで、クライアントへの適切なアドバイスに直結する内容となっています。国際相続案件への対応力を高め、クライアントの信頼に応えていくためにも、この機会に確かな知識と実務スキルを習得されることをお勧めいたします。
セミナー内容
●国際相続案件の基本を理解するために知っておきたい税務の基礎
●国内と海外の税制の違いと財産評価方法
●実務で役立つ国際相続の具体的事例(国籍×国内居住×海外居住)
●士業として押さえるべき、国際相続における税務の留意点
●国際相続の生前対策:相談できるアドバイスの内容と方法
※この内容は、2025年2月12日に撮影された内容になります。ご了承ください。
動画セミナーの詳細・購入をご希望の方は下記のリンクをご覧ください。
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]