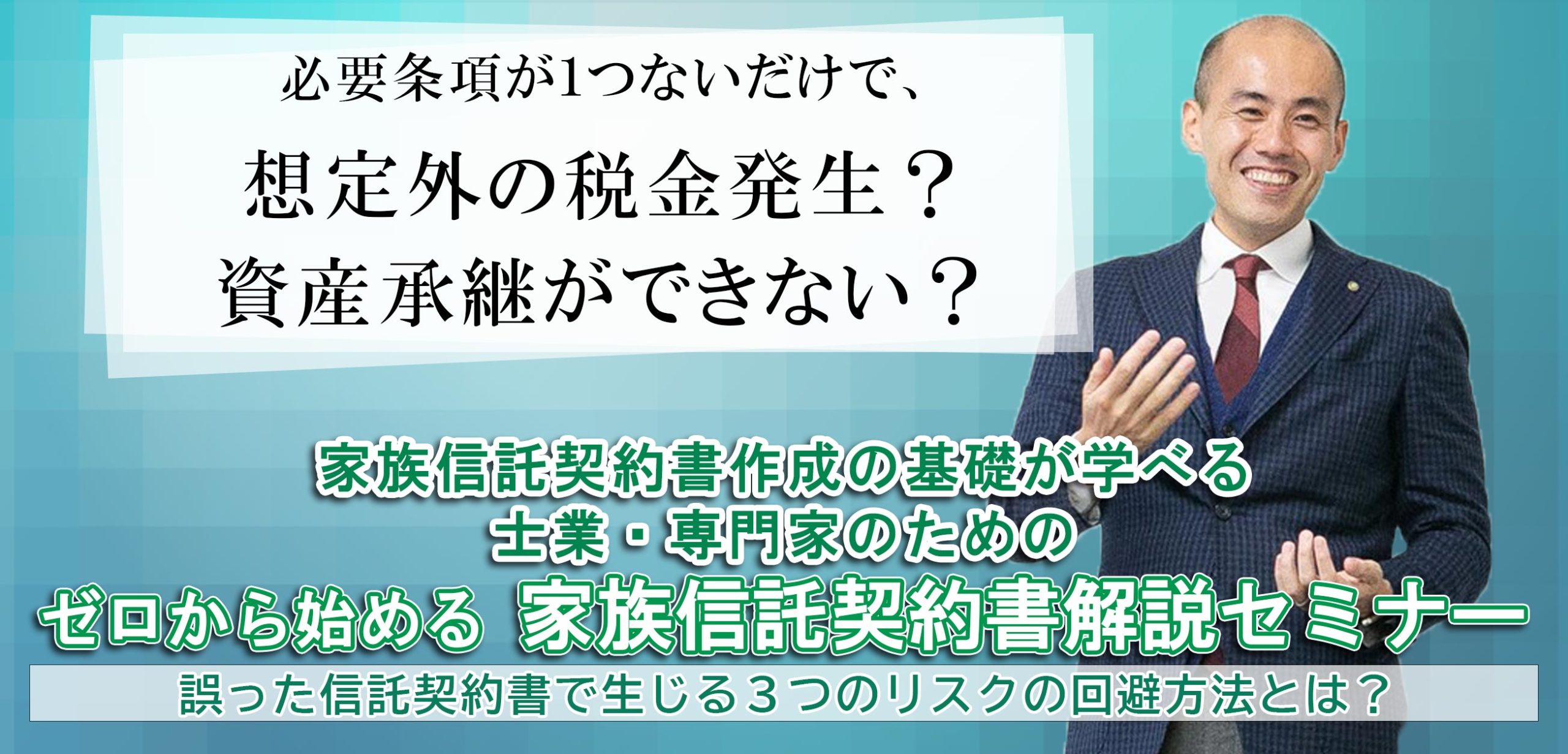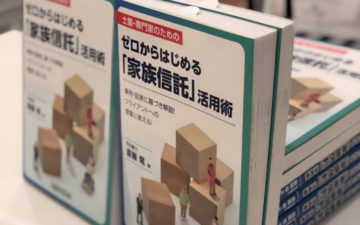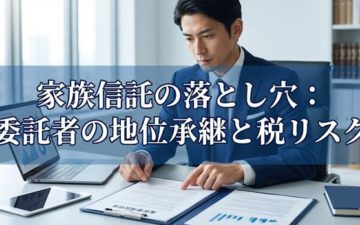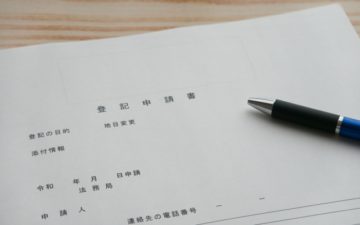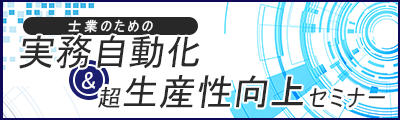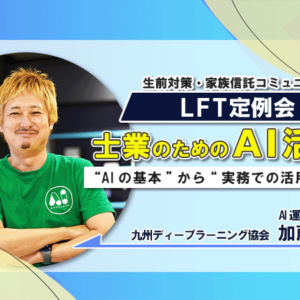家族信託は、認知症対策、相続対策ツールの一つとして多くの専門家が手掛け始めています。その運用に当たり、家族信託をすると、特に収益不動産のオーナーなど依頼者が今まで行っていた確定申告の内容から、家族信託特有の手続きをする必要があるという点が発生します。
家族信託を取り扱う士業や専門家としては、依頼者へのアドバイスやサポートに際してこれらの情報を理解し、適切に取り扱うことが必須です。
今回の記事のポイントは下記の通りです。
- 家族信託した場合でも、受託者ではなく受益者が確定申告を行う義務がある
- 信託期間の設定や固定資産税の取扱について、信託設定時に留意する
- 収益が年間3万円以上ある財産を家族信託した場合など、受託者による信託計算書等の提出が必要なケースを理解しておく
- 信託財産を譲渡した場合、譲渡税が発生し、受益者が申告を行う必要がある
- 信託不動産の損益通算ができない点に注意する
家族信託後の税務上の手続きと依頼者へ説明する際のポイントについて解説します。
目次
家族信託導入後の受益者の確定申告
家族信託が成立した後も、受益者は従前と同様に確定申告を行う必要があります。信託財産の管理と収益計算は受託者の役割ですが、得られた収益は受益者に帰属します。従って、納税義務者は受益者個人となり、受益者名義での確定申告が必要です。
家族信託導入後、不動産収入がある受益者は確定申告の際に新たな資料を提出する必要が生じます。
信託不動産の所得明細の提出
信託対象の不動産から収益(例:家賃)が生じた場合、関連する不動産所得に関する明細書が要求されます。具体的には「青色申告決算書」もしくは「収支内訳書」を作成し、信託不動産の収入(家賃)や経費(管理費、固定資産税など)を明記した所得明細書を添付する必要があります。
受益者が複数の信託契約を持つ場合や、信託財産と個人所有の不動産が混在している場合、各信託や所有形態ごとに損益計算を明確にした明細書を提出する必要があります。
実際には、受託者である親族が受益者の名義で申告をサポートすることになるとは思いますが、家族信託が導入された後でも、受託者名義で確定申告をするのではなく、受益者が確定申告をする必要があることを説明する必要があります。
固定資産税の取り扱い
固定資産税の納税通知書は、受託者名義で送付されますが、その中には受託者の個人所有不動産と信託不動産が混在して記載される場合が多いです。受託者と受益者間で、どの部分が信託不動産に関連する税金で、どの部分が受託者自身の税金に該当するかの明確な区分と計算が要求されます。税法上、信託財産は受益者の所有と見なされるため、信託不動産に関する計算を正確に行い、誤りのない申告を行うことが重要です。
受託者による信託財産収益の報告と信託計算書の提出
家族信託を開始した後には、受託者による財産管理業務がスタートします。受託者が行う税務関係上の役割は次の通りです。
受益者への信託財産収益の報告
信託法上、家族信託の受託者は、信託財産からの収益の計算と受益者への報告、そして分配の義務が伴います。特に、不動産を信託財産として持つ場合、家賃収入や固定資産税、さらには建物の修繕費用などの収支状況が生じます。信託財産の状況を年1回以上、受益者に適切に報告する必要があります。
税務署への信託計算書の提出
税務上、年間での信託財産収益が3万円を超える(1年未満の計算期間の場合は15,000円以上)場合、受託者は「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」を作成し、1月31日までに受託者居住地の管轄の税務署に提出する義務が生じます。
受託者が海外在住の場合も、日本における最後の居住地の税務署への提出が要求されます。
信託対象が自宅や預金の場合の取り扱い
信託財産としての自宅や預金が収益を生まない、または年間収益が3万円未満の場合、上述の信託計算書の提出は求められません。従って、家族信託の目的が主に預金の管理や家屋の維持であれば、特別な税務手続きは不要となります。
信託の計算期間の設定
受託者は、受益者に年1回、信託財産の管理状況の報告を行う義務があります。この報告の計算期間を、確定申告の集計期間(1月1日から12月31日)に一致させることで、実務上の計算手続きを簡素化できます。これにより、受益者への報告と確定申告の両方の手続きを効率的に進行させることが可能です。
依頼者へ説明が必要な家族信託後の各種特例適用と注意点
家族信託を導入するにあたって、各種特例や税務上のリスクがあることを事前に伝える必要があります。以下では、家族信託に関連する主要な税務上の注意点と特例を解説します。
信託不動産の譲渡と税務
信託財産の譲渡が行われた場合、その収益については確定申告が必要です。受託者が信託財産の譲渡を行う際、税務上、それは受益者が財産を譲渡したものと解釈され、受益者に譲渡所得税が適用されるからです。
居住用財産の3,000万円特別控除の適用ができる
受益者本人の居住目的で使用している不動産の売却には、一定の条件下で3,000万円の特別控除が認められます。この控除は、信託財産として管理される不動産にも適用可能です。したがって、家族信託を使用している場合でも、必要な要件を満たすことで、この控除を活用することができます。
参考:国税庁HP
No.3302 マイホームを売ったときの特例
法令解釈通達/第2所得税に関する取り扱い2-52
相続空き家3000万円特別控除が適用できない
相続空き家3000万円特別控除が適用できない
2022年12月20日に東京国税局の文書回答事例において、信託終了後の不動産について相続空き家特例は適用できない文書が公開されました。信託終了後に帰属権利者が取得した信託不動産については、相続後の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けられないという回答内容です。
昭和56年5月31日以前建築の戸建てについては、一定の要件を満たせば相続空き家特例が適用できるのですが、家族信託後の不動産については適用ができません。
https://s-legalestate.com/notapplicable-vacanthouses
家族信託後の受益者の所得と信託不動産の損益通算禁止
信託不動産からの不動産所得がある場合には、依頼者への説明が必要です。
家族信託前は、収益と損失の通算は可能ですが、信託不動産に関しては例外的な取り扱いがあります。信託不動産からの所得に関する損失は、他の信託財産や受益者個人の所得とは通算することが認められていません。また、損失の繰越しに関しても同様の制約が存在します。
例1: 信託財産が赤字、他が黒字のケース
信託財産からの所得が-300万円の損失で、受益者の所得が400万円の黒字の場合、信託財産の損失は通算されず、受益者の400万円がそのまま課税の対象となります。
例2: 信託財産が黒字、他が赤字のケース
信託財産からの所得が400万円の黒字、受益者の所得が-300万円の損失の場合、受益者の損失は信託財産の所得と通算されることが認められます。結果、課税対象となる所得は100万円となります。
上記のような特例などが適用できない点を考慮すると、家族信託の利用によって税負担が増加する可能性が考えられます。特に、多数の不動産を所有している場合、どの不動産を信託財産として設定するかは、中長期的な税負担の観点から極めて重要です。専門家として、依頼者への状況や目的に合わせた最適なアドバイスと戦略の提供が求められます。
まとめ
- 家族信託した場合でも、受託者ではなく受益者が確定申告を行う義務がある
- 信託期間の設定や固定資産税の取扱について、信託設定時に留意する
- 収益が年間3万円以上ある財産を家族信託した場合など、受託者による信託計算書等の提出が必要なケースを理解しておく
- 信託財産を譲渡した場合、譲渡税が発生し、受益者が申告を行う必要がある信託不動産の損益通算ができない点に注意する
家族信託は資産の管理や相続対策に有用ですが、多くの税務上の手続きと注意点があります。特に税務上のリスクについて説明していなかった場合には、専門家の説明責任不足につながりかねません。
最新情報を収集して適切なアドバイスができる体制をつくっておきましょう。
家族信託契約書を作成する際にどのように設計・起案していますか?
家族信託というのは、士業・専門家にとって遺言や成年後見では対応できなかった範囲をカバーできる「一手法」です。自由度が高い分、お客様のニーズにあわせた対策を設計できます。しかし、一方で、オーダーメイドの契約書というのは経験も必要。そして、制度の歴史も浅く十分な判例もない状況も重なって、なかなかハードルが高く感じる方もいらっしゃるでしょう。
特に、家族信託契約書作成になると士業・専門家の技術が問われます。
もし、間違った信託契約書を作成してしまうと、本来支払う必要がない税金が課税されてしまう、金銭を管理する信託口口座が開設できない、一つの条項がないだけで不動産の売却処分等ができないといったリスクが発生してしまいます。
ここができるのとできないのとでは、士業・専門家にとっては大きな差でもあります。
今回、家族信託組成数400件を超える信託サポート件数TOPクラスのリーガルエステートがその信託契約書の最新情報とともに、作成手法について解説します。
こんな方にオススメです
・これから家族信託をやっていきたいと思っている方
・家族信託契約書を起案する方
・顧問先や顧客に家族信託を提案し、他の士業につなぐ方
セミナーでは、家族信託契約の内容と法務、税務の中でも特に重要なことをダイジェストでお伝えします。
【士業・専門家のためのゼロから始める家族信託契約書解説セミナー】
今回のセミナーでは、主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。
- 間違った信託契約書を作成した場合の3つのリスク
- 無駄な税金を払わず、預金口座凍結を防ぐための家族信託契約スキームの徹底解説
- 契約書で要注意!自益信託と他益信託。契約時に想定外の税金がかかることも!?
- 不動産所得がある顧客には要注意!知っておきたい損益通算禁止のリスクと回避方法
- 信託契約後の金銭を管理するための信託口口座の開設手続きの流れ
- 不動産が売却できない!を防ぐための信託契約条項と登記の方法は、ズバリこれ
- 委託者の想いを叶える財産の引き継ぎ方と契約書の定め方とは?
- 信託終了時に想定外の税金が!?信託契約で絶対もれてはいけない契約条項
- 適切な資産承継を考えるためには出口戦略(終わり方)が重要
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]