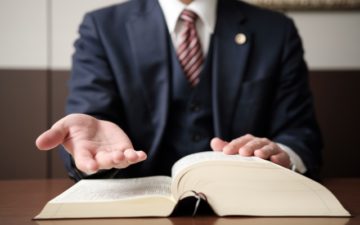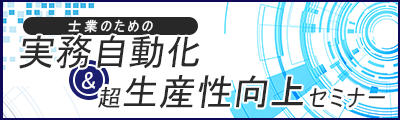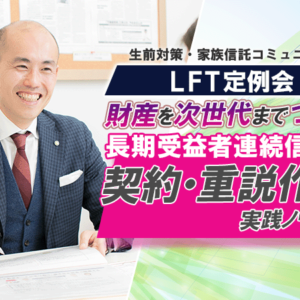紹介案件を獲得するために会社を訪問する、そして、営業担当者向けに勉強会を開催するという方法は金融機関や不動産管理会社など社員数10名超の企業と業務提携をする方法として有効です。もう一つの方法として、同じ価値観を持つ自分の周辺業務に携わる異業種の専門家と連携して仕事を受注していくといった方法として、コミュニティの運営があります。
コミュニティを運営することにより、自然とその地域におけるその先生が手がける分野の情報が集まりやすいポジションをつくることができ、紹介件数を増やしていくことができます。
今回の記事のポイントは次の通りです。
- コミュニティ運営により、業務が発生したときに相談(紹介)を先に受けることが見込める
- コミュニティづくりを考える際には、参加者の絞り込み(誰を)、参加するメリット(特典)、有料とするか無料とするか、何を成し遂げたいのかの4つの要素から設計していく
- 異業種からの紹介案件を獲得することを主に考えるのであれば、無料でのコミュニティ運営を、参加者にとって本当に業務に役立つノウハウを提供し続けていけるのであれば有料での運営という形で使い分けを考える
- コミュニティ運営にあたっては主催者の定期的な情報発信による信用残高を高め、主催者が何をしたいのかを伝えることが必要
- 4つの要素をチラシ、HPなどに形にすることにより、紹介案件獲得の営業活動に加えて、コミュニティ参加者促進という一つの営業ツールとして活用していくことができる
異業種からの紹介案件を獲得したい先生向けに、どのようにコミュニティ運営に取り組んでいくのかをお伝えします。
目次
異業種連携ができるコミュニティとは?
コミュニティとは、広い意味でとらえると、共通の価値観をもつ、人の集まりです。
今回の記事で解説するコミュニティでは、相続、助成金、起業などのある専門分野に関連する業種の人の集まりです。コミュニティでは、お互いのビジネスの発展のために運営します。その分野に属する人が増えれば増えるほどお互いの情報が交換され、成功事例の情報が増える、メンバー同士の紹介が発生するという相乗効果が発生できます。
特に主催者になると、必然的に情報も集まりやすいので紹介案件が増えるという効果が発生します。
コミュニティづくりを考える際には、下記の4つの要素を設計していく必要があります。
・参加者の絞り込み(誰を)
・参加するメリット(特典)
・有料とするか、無料とするか
・何を成し遂げたいのか
以下、上記を説明していきます。
参加者の絞り込み:誰を対象にするか
コミュニティ運営もサービス提供と同じく、まず最初に考えるべきことは誰に参加してほしいのか、どんな人に集まってほしいのかを明確に設定することが必要です。
紹介してほしいお客さんと関連している業種は何か?ということをまず考える必要があります。前回の記事で伝えた紹介先(BtoB)開拓と同じく、自分が理想とする顧客名簿を持っている業種を考えます。
例えば、中小企業の会計顧問や相続などの紹介案件を獲得するということであれば、金融機関などが想定されます。でも、コミュニティ運営を考えるにあたっては、金融機関といった企業というよりもむしろ、個人的な属性が強く、むしろ個人事業主や中小企業経営者が対象になります
僕自身も過去にやってしまった失敗事例ですが、金融機関や不動産会社などの営業マンやスタッフにも参加を促していた時期があります。独立志向が高い、勉強する意識が高い人は積極的に勉強会などに参加してくれる傾向が高いですが、一般的なサラリーマンは業務時間以外に勉強するという意識が弱いため参加率は低いのです。むしろ、勉強する意欲がある人は全体でいうと2割程度です。企業のサラリーマンに対しては、むしろその会社と業務提携を行い、現場スタッフ向けの勉強会を開催し、〇〇という業務が発生したら〇〇先生に紹介すればいいといううような意識を付けることを重視したほうが効果的です。だから、時間よりもむしろ接触するための回数を重視して、勉強会数を増やし、勉強会時間は減らした方がむしろいい。皆、長い話は聞いていられないので、僕が最近やる企業向けの勉強会は時間を短くし、回数を増やす方向で行っています。
そのため、コミュニティ運営で参加するメンバーは、上記の事例でいうと金融機関などの対企業というよりもむしろ、中小企業経営者(士業・生命保険代理店の経営者)や個人事業主としての特性が強い外資系生命保険営業マンなどが対象になります。これまでの、対企業向けの紹介先開拓とは意識を変える必要があることに注意をしていください。むしろ、コミュニティ運営は勉強意識が高い個人が対象となります。積極的に自らの業務に必要な情報を収集しにいく個人を対象に組み立てていく必要があります。
コミュニティに参加するメリット(特典)は何か?
コミュニティもサービス提供と同じく、商品の設計が必要です。
つまり、設定した参加者が具体的に参加するメリットは何なのか?というところをしっかりと打ち出していく必要があります。
そもそも、その地域、業界での発言力が高い、著名であるといった先生であればその先生の話を聞きたい、情報を得たいという人が多いのでそこまで魅力的な特典を作る必要はありません。ですが、そうではなくこれから取り組む先生にとってみれば、その人の話や集まりに参加する要素が当初ないので、参加するメリットがないのです。
そうなると、その主催者のコミュニティに参加するとどのようなメリットがあるのか、ということをわかるような形で作りこむ必要があります。
・定期的な勉強会、セミナーへの参加権利
をベースとして、他にどんなものが用意できるか考えていくとよいです。例えば、
・参加者がお客様へ説明するための販促物の提供
・参加者限定のイベント
・無料相談、無料診断サービス
・参加者限定のFacebookグループの運営、メルマガ(ニュースレター)発行 など
このように参加者にとって魅力的な特典として、自身のサービスでどんなサービスを参加者に対して提供できるのか考えてみましょう。このようなサービスがあったら便利だという目線で考えていくといいです。生命保険営業マンが知りたい法律や税務、お客様提案方法の勉強会やお客様向けの説明資料、無料相談などのサービスなどが考えられます。
介護事業者向け、税理士向けなど自分がつくりたいコミュニティの参加者目線でその参加する業種がほしいサービスを考えてみてください。
コミュニティの参加費は有料とするか、無料とするか
コミュニティを運営するにあたっては、時間とコストがかかります。
参加費を無料とするのか、有料とするのかによって、どの層が参加するのか、どの程度のサービスを提供するのかといったことが変わってきます。
当然、無料だと参加者は集めやすいし、離脱は少ないです。
有料課金されないため、ゆるやかにつながり続けることができます。ですが、その反面、勉強しようという意識が弱い方も参加する傾向があるため、お互いの業務につながらない、参加者同士のコミュニケーションが生まれづらいという状況が発生します。また、無料であるため主催者も時間と労力をかけられません。
私自身も過去、事務所付近の不動産管理会社、会計事務所などを対象としたゆるやかなコミュニティづくりの一環で勉強会を開催してきたことがあります。運営するにあたってはDMなど集客コスト、会場費のほかスタッフの時間を割くなどそれなりにコストがかかります。有料だと意識が高い参加者が参加する反面、低額の課金でも離脱率が高くなります。また、参加を維持するためにコンテンツや特典の定期的な提供などが必要です。
異業種からの紹介案件を獲得することを主に考えるのであれば、無料でのコミュニティ運営を、参加者にとって本当に業務に役立つノウハウを提供し続けていけるのであれば有料での運営という形で使い分けを考えていくべきです。
成し遂げたいのかをきちんと伝える
コミュニティを運営するにあたっては、主催者としてなぜ運営するのかという想いをきちんと伝えるということが求められます。やることになったきっかけ、そして何を成し遂げたいのかというストーリーが大切です。
コミュニティ主催者となるにあたって必要なのが情報発信力です。その地域、分野において役に立つメルマガ、セミナーなどの情報発信をし、役に立つなとその先生の信用残高を高めておく必要があります。前提として前項で伝えた隣接業種(BtoB)への定期的な情報発信を行い、その先生の主催するコミュニティに参加してみたいという信用残高を貯めておくことが必要です。
僕自身は、今は、相続や家族信託を手がける士業や専門家向けのコミュニティを運営しています。僕自身大手不動産業者から突然仕事を切られるといったことをきっかけに自分自身の仕事を下請け的な仕事から切り替えていったという経験を元に、自分自身の仕事を下請けではなくパートナーとして、そしてお客さんの問題解決ができる提案型の仕事へと変えていきました。そのような経験を経て、今は規模拡大を目指すというよりもむしろ、僕と同じような先生が今後手続的な仕事から少子高齢化、認知症問題、法律、税務など複雑化した時代において、お客さんの問題解決ができる本当の専門家が増えればと思い、コミュニティを運営しています。
主催するリーダーが大切にする価値観、想いをきちんと伝えることで、一緒に行動していきたいと考える参加者が増えてきます。人間は感情で動く生き物です。共感できるストーリーを伝えられるようにしてください。
ここまで伝えてきた、①参加者の設定、②コミュニティーに参加するメリット(特典)、③コミュニティの参加費は有料とするか、無料とするか、④何を成し遂げたいのか、この4つをきちんとチラシ、HPなどの形にすることで、参加者に案内できるようになります。これにより、今までは紹介案件獲得という営業手法のみだったのが、コミュニティへの参加への誘導という選択肢としても活用することができるようになります。
まとめ
- コミュニティー運営により、業務が発生したときに相談(紹介)を先に受けることが見込める
- コミュニティづくりを考える際には、参加者の絞り込み(誰を)、参加するメリット(特典)、有料とするか無料とするか、何を成し遂げたいのかの4つの要素から設計していく
- 異業種からの紹介案件を獲得することを主に考えるのであれば、無料でのコミュニティ運営を、参加者にとって本当に業務に役立つノウハウを提供し続けていけるのであれば有料での運営という形で使い分けを考える
- コミュニティ運営にあたっては主催者の定期的な情報発信による信用残高を高め、主催者が何をしたいのかを伝えることが必要
- 4つの要素をチラシ、HPなどに形にすることにより、紹介案件獲得の営業活動に加えて、コミュニティー参加者促進という一つの営業ツールとして活用していくことができる
紹介案件を獲得する手段の一つとして、コミュニティー運営について解説しました。対企業は業務提携がポイントですが、士業経営者、中小企業経営者、個人事業主などはコミュニティ運営が有効です。何もないなか、いきなりコミュニティをつくっても参加者を集めることはできません。まずは自分に興味をもってもらう、話を聞いてもらえるファンをつくらなければ、参加者を集めることは難しいです。
コミュニティーをつくっただけでは成立しないということは注意しておいてください。地域でのある分野でのコミュニティーをつくる、これは、今からでも可能です。
次の士業・専門家のビジネスモデルを構築するには!?

士業は、資格という安定した肩書があるからこそ、国民に広く信頼されており今の士業という仕事があります。
その反面、どうしても資格という枠に捉われ過ぎがちな面があり、本当は色々できるのに、チャレンジできる土台があるのに、〇〇士は〇〇いう業務しかできないという、自分の枠を狭めてしまっていがちです。そして、ある程度、地域の信用を得て仕事を受注できるようになると、「こんなものでいいかも・・・」と思い込んでしまい、小さくまとまってしまいがちです。でも、本当は先人たちがゼロから築きあげた資格、その信用があるから今があり、次の時代の士業につないでいく責任があります。
インターネットが普及し、民間会社がリーガルテックの分野に参入してくるなか、士業はそのまま何もしないでやられっぱなしでいいのか??そんな訳はありません。
なによりも危険なのは変化をしないこと、新たなチャレンジに勇気をもって踏み出せなくなることです。
チャレンジするということは、当然、失敗する可能性も含まれます。
でも、失敗して失うものなど、たかが知れています。
今後、我々は時代の流れを受けてチャットツールやZoomなどオンラインの仕事の進め方を本格的に学んでいく必要性があります。
そんな中、下記のような悩みはありませんか?
・AIやデジタル化による 手続き業務の減少 に不安を感じている
・紹介に頼る経営から脱却できず、売上が不安定 だ
・新規顧客を獲得したいが、オンラインの活用法がわからない
・価格競争 に巻き込まれ、付加価値の高い業務ができていない
・常に新規案件を探し続ける 自転車操業 から抜け出したい
どのように士業・専門家業務をオンラインに変えて、手続き代行ビジネスからコンサル型ビジネスへと変えていき、継続的な顧客獲得と育成の仕組みを構築していけばいいのか、斎藤が取り組んできた事例を元にWEBセミナーにてお伝えします。
士業のための新・収益モデル構築セミナー
セミナーでは下記の内容を伝えています。
- AI時代のマーケットと士業の未来
- 「手続き業務」から脱却する高収益案件の発想
- 価格競争に陥らないオンライン集客と商品設計
- 見込み客を自動で集めるためのペルソナ設定と情報発信
- ChatGPTを活用したコンテンツ作成の効率化と実践法
- オンラインとリアルを融合させた高確率な個別相談への誘導術
- 単発業務をストック収益に変えるアフターフォローと顧問契約
- 顧客のLTV(生涯顧客価値)を最大化する全体戦略
- AIを活用し、人にしかできないコンサル業務で選ばれる専門家になる方法
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]