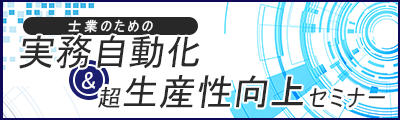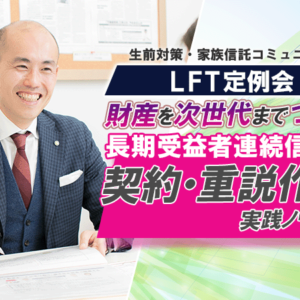6月後半に入り、緊急事態宣言も解除されようやく問い合わせが増えてきた感を感じています。今まで、自粛で動けなかったお客さんが動き出してきている、そんな状態です。営業活動も自粛していた、やりづらかった、そんな状況から変わりつつあります。そんな中、これから相続や信託を扱っていこうという先生がどのような取り組みをすればいいのか、といった相談を受けることが増えてきました。
今回の記事のポイントは下記の通りです。
- コストを掛けず、新規開拓を行うのであればエンドユーザー開拓よりも紹介先開拓を優先すべき
- エンドユーザー(BtoC)と企業(BtoB)とでは悩みや課題は異なる。同じものを提供しても相手に刺さらない
- 顧客の悩み、課題は何かからサービスを考える。優先すべきは相手のメリット
- 提案内容は資料にまとめ、見える化する
緊急事態宣言が解除され、これから営業活動に取り組もうと考えている先生が何から取り組むべきなのか、参考になれば幸いです。
目次
大手にはできない、地域の紹介先開拓に力をいれるべき
エンドユーザーを狙って広告費を投入しチラシを撒く、ネット広告費を出す、ブログや動画、SNSなどのコンテンツ作成に時間をつかう、、。これから仕事に取り組むにあたって、大手事務所が全国を相手にネット広告のみならず、ブログ投稿によるSEO対策のほか、YouTubeなどの動画活用など時間も資金も大量に投入している状況では成果を出すには相当の労力と時間がかかります。最近は民間企業も相続業務のみならず会計なども含めて士業が提供するサービスを取り扱うようになりつつあります。
そんな状況の中、大手が出来ないことをやっていく必要があります。それは、地域での紹介先開拓です。僕自身も開業当初に徹底的に行いました。地域で接点をつくる、人間関係をつくるという部分は大手にはやりづらい戦略です。接点をつくるには、自分の足で実際に会いに行き、名刺交換をし、その人の悩みを引き出し、ひとつずつ解決していく、信用の積み重ねが必要です。

元々、長年ビジネスをしていれば、既存の長い付き合いのある同業者が必ずいます。その中であえて取引先を変える必要性が全くないのです。既存の同業者に割り込みつながるためには、自分がつながりたい人目線で何か役に立てることはないのかを徹底的に考えていく必要があります。
紹介先の悩みはエンドユーザーとは異なる

エンドユーザーと企業では悩みや課題は異なります。
エンドユーザーは、自身の家族や財産のことの相談が主でありその解決方法として、本来の士業サービスが求められる高い傾向があり、提供するサービスも元々手掛けているサービスが当てはまりやすいです。しかしながら、企業や他士業・専門家など(BtoB)を相手にエンドユーザーを紹介してほしいという紹介先開拓という面で企業目線で考えると、エンドユーザーの悩み、か課題と紹介元の悩み、課題は異なります。
紹介先(BtoB)開拓で意識しておかなければならないのはここを間違えていると紹介元の課題は解決できないばかりか、お客さんを紹介してほしいという、仕事だけを求める下請け的な仕事の受け方にになってしまいます。
例えば、紹介元である企業(BtoB)が仕事を大量に抱えていて、外注先を増やしたいという状況であれば、本来業務中心の下請け的な受注方法でも仕事は受注できます。しかし、同じような業務を取り扱う競合が多い状況であれば、現在付き合いのある外注先がいれば新規に取り入ることは容易ではありません。例えば、私は司法書士をやっているので登記という商品もありますが、紹介元に提携司法書士が元々いて、その事務所で十分に仕事が回っており外注先に不満がなければ、つけ入る余地がないんです。
紹介先開拓においては、本来業務ではそもそも相手の課題は解決できない可能性があり、直接の業務以外の部分で問題解決をしていく必要があるということの理解が大切です。
紹介元の悩み、課題から問題解決をしていく
では、 どうやって紹介元の悩みや課題を把握するか、それは直接相手に聞くのがベストです。もし、直接聞く機会がなければ、Yahoo 知恵袋などでそのお客さんの業種が悩みに持ちそうな質問をピックアップしてその回答を探るなどを行ってます。その業界に関するたくさんの質問と回答が網羅されているので、あたりをつけられるはずです。
例えば、エンドユーザー(BtoC)であれば、相続に関する悩みとして、認知症、資産承継、節税などの悩みがありますが、紹介元(BtoB)でいうと、ビジネスを行っているため、常に”人” 、”物”、”お金”の問題で何かしら悩んでいます。これは、私もそうです。
この三つのキーワードを基準にどんなことで悩んでるのかといったことを考えていきます。

それらの課題や悩みを自分が持っているサービスや人脈で解決できないかということを考えていきます。全て自分で解決できなくてもそれらを解決できる人を紹介するだけでも相手の課題を解決するお手伝いをすることができます。
相続・家族信託案件でいうと、オーナーさんを抱えている不動産管理会社、高齢者の医療保険などを提案している保険代理店、賃貸収入がある個人の確定申告をしている会計事務所などなど、相手の立場で何が必要なのか、何が課題なのかを業界の事前分析や顧客とのヒアリングを通じて考えていくわけです。いきなりお客様を紹介してほしい、協業してほしいと依頼しても、元々、その取引先と強い信頼関係があれば別ですが、そうでない限り、通常は一緒に組んでくれません。
それは、あなたと組む理由が何もないからです。そもそも、よく知らない相手と組むことは、リスクがあります。優先すべきは、自分より相手のメリットです。
相手の立場に立って、あなたと協業してあなたと組む理由は何か?組むことによって得られるメリットは何か?(新規顧客獲得、顧客満足度向上、業務効率化など)断られるとしたらどんな理由か?それらをよく考える必要があります。相手のメリットが大きくなるような提案をしなければならないし、その提案が自分のみが有利となる依頼で、相手の利益が少なければ、そんな紹介依頼は誰も受けません。
メリットがないと人は動きづらい
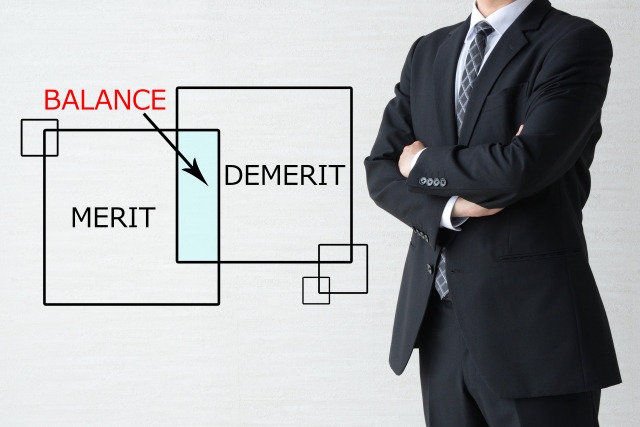
例えば、 紹介元の悩みとして下記のような悩みがあるということがわかったとします。
・コロナの影響で売り上げが減少している
・集客が上手くできていない
・商品単価が低く、単価を上げていきたい
・人材教育まで手が回らない などです。
では、何を提案していくのか?
例えば、売上だったら集客のお手伝い、相談会の共催、セミナーの共催、集客用のチラシやウェブ用の記事のライティング、紹介元のお客様に対するサービス商品付加の提案などができます。自分ができることで何が貢献できるだろうと考えていくんです。相手にとってメリットがある提案が必要です。
売り上げを上げたいという要望に対しては、既存のお客さんに対して更に提供するサービスを増やすという提案もできます。既存のお客さんに対して提供する方が新規開拓よりも手間がかからないからです。僕自身も、協業したい紹介先のためにお客さんに配布する相続のチラシを制作したり、小冊子を代わりにつくるといったことをやりました。そして、もっと踏み込んでできるのであれば、紹介元のスタッフが自分たちでお客さんに相続関連のアドバイスをできるよう社内勉強会を開き、紹介元で案件を受注してもらってその過程で発生した案件の契約書作成や登記業務を本来業務として受注するということも行いました。
紹介元によっては、業務効率化を検討しているようあれば、ITツールを使った業務効率化の方法や、集客やWebコンテンツ作成のサポートなども提案できます。紹介元の役に立てることで信用を得て、そこから本来業務の受任へとつなげることできるのです。
もともと士業・専門家が兼ね備えている”信用・信頼”という資格、武器を活かして、+αで業務改善提案することにより、紹介元の課題解決提案ができます。その結果、紹介案件獲得につなげることができるのです。
まずは、その紹介元の悩みに対してどんなことを提供できるのか、役に立てそうか考えてみて下さい。
資料にまとめ提案する(見える化する)
顧客に解決するサービスを提案するためには、目に見える形で届けることがポイントです。 実際に目で見て、イメージできないと人は動けません。皆さんも、形になっていないサービスはイメージできないのではないでしょうか?言葉だけではイメージできないものも、目で見て確認できる資料やイメージ図があると考えることができるようになります。

課題とお手伝いできることをまとめた”提案書”という形で見える化することがポイントです。
上記のように形にすることで紹介元は検討できますし、提案した紹介元の相手の決裁権者にもみてもらい判断できる材料となります。まずは、思いついたものを提案書という形で届ける発想をしてみてください。形にしないと相手に届かないし、次のステップに進めることが難しいです。形にすることで、この先生は仕事ができると相手に感じてもらえるというメリットもあります。
このようなことをできるようにするためには、常日頃からアンテナを立てておき情報誌を収集をしていく必要があります。私自身も、その業界の現状、働いている人たちの悩み、課題などをネット、書籍、セミナーなどで情報を仕入れることで当たりをつけてきました。この試行錯誤を続けていくことで紹介元が抱えている悩みや課題などの共通項がわかり、自社が提供できるサービスの内容もその都度工夫して提案するなど、考える材料が増えてきて、精度を上げることができるようになるんです。
このように顧客の課題に対して自社でできるサービスを付加価値として提供する、そこから貸しをつくり顧客紹介につなげる、場合によっては、新規のサービスとして有料化することもできます。私の場合も当初は本来業務受注をするための無料サービスだったものが、今は、企業向けの集客支援として顧問契約の有料サービスを商品化しています。
まとめ
- コストを掛けず、新規開拓を行うのであればエンドユーザー開拓よりも紹介先開拓を優先すべき
- エンドユーザー(BtoC)と企業(BtoB)とでは悩みや課題は異なる。同じものを提供しても相手に刺さらない
- 顧客の悩み、課題は何かからサービスを考える。優先すべきは相手のメリット
- 提案内容は資料にまとめ、見える化する
本来業務以外の部分で業務改善の提案をしてお客さんの役に立つ、こういった地道なことの積み重ねで相手から信用を得ていくことができます。本業以外の部分で相手の役に立ち信用を得ることで、本業につなががった、そんな経験を僕自身も経てきました。
これから、本来業務とは違った形で、我々が求められるサービスが変わっていくでしょう。考え続け、試行錯誤することで新たな仕事や新しいつながりができてきます。
提案型業務に変えていくには?
新型コロナの影響でリアルからオンラインへと仕事の流れが、大きく変わりつつあります。
時代の流れを受けて対面営業に加えて、チャットツールやZoomなども活用した仕事の進め方を本格的に学んでいく必要性があります。
そんな中、下記のような悩みはありませんか?
・新規顧客開拓をし続けるのが苦しい
・手続きビジネスから脱したい
・高額コンサル販売方法がわからない
・WEB・IT活用に苦手意識がある
どのように士業・専門家業務をオンラインに変えて、手続き代行ビジネスからコンサル型ビジネスへと変えていき、継続的な顧客獲得と育成の仕組みを構築していけばいいのか、斎藤が取り組んできた事例を元にWEBセミナーにてお伝えします。
【オンライン開催】
家族信託・生前対策集客・受任力アップセミナー
会場:オンライン配信のみ(ZOOM活用)
定員:各回8名限定
★こんな方を対象としています★
〇手続き代行ビジネスからコンサル型ビジネスに変えていきたい方
〇喜ばれる仕事を直接、顧客から受託したい方
〇高単価生前対策・家族信託コンサル案件の受任の考え方を学びたい方
〇生前対策・家族信託コンサル案件の集客の仕組みづくりを知りたい方
〇IT・AI化が進む中、今後の士業・専門家の働き方を見直していきたい方
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]