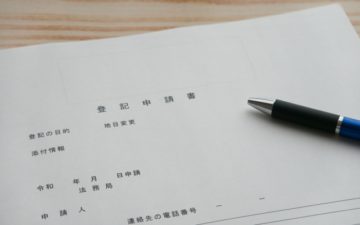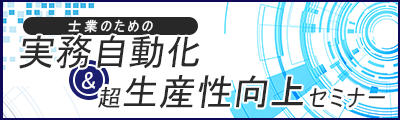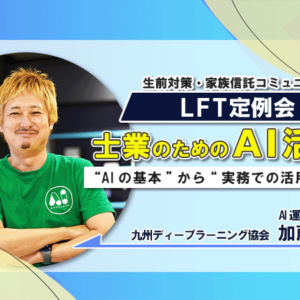農地を所有している方の相続対策、生産緑地対策として、家族信託・民事信託を活用していきたい、一般の方や同業の専門家からもそんな相談を受けるようになってきました。生産緑地を含む農地については、農地法という法律に規制があるため、必ずしも農地を信託できるとは限りません。
今回の記事では、どのように農地の信託スキームを考えていけばよいのかということをテーマにお伝えします。
- 農地のまま信託できない
- 現況が宅地であれば、登記地目が農地でも信託できる
- 現況が農地の状態で、将来の宅地転用に向けた対策を立案する場合には?
- 農地を宅地に転用し、家族信託・民事信託するための方法
それでは、どうぞ(^^)/
目次
農地のまま信託できない
農地についての判断ポイントは現在の利用状況が農地か、否かです。
現況が農地の場合には、農地法の適用を受けるので、農業委員会の許可又は届出(以下、「農業員会の許可等」といいます。)がないと信託をすることができません(農地法3、5等)。
農地を信託財産とする信託契約は、農業委員会の許可等が効力発生要件です。
そのため、農地以外の金銭、アパートを信託財産とした場合には、農地以外については契約時から効力は生じますが、農地については信託契約の効力は生じません。
そして、農地のまま信託の受託者となれるのは、農業協同組合など一定の法人に限定されており、子など家族を受託者とする信託では、許可等を得ることは難しく、結果、信託を行うことはできません。
現況が宅地であれば、登記地目が農地でも信託できる
土地が農地法の適用を受けるかどうかのポイントは、登記簿上の地目ではなく、現在の土地の利用状況です。
相談事例でも多いですが、過去、市街区域内の農地を住宅建築に伴い宅地化したものの、地目変更登記をしないまま、アパートを建てたような事例では、現況が農地でなく宅地なので(固定資産納税通知書上も登記地目が畑など農地、現況が宅地として登録されているはずです)、その場合は、信託契約を行うことができます。
ただし、登記をするにあたっては、法務局は登記地目を基準に登記の受理判断をするので、前提として現況の利用状況に併せて、地目変更登記をする必要があります。
そのため、現況が宅地であれば、地目変更登記をすれば信託契約はできます。
意外と、信託を専門とする専門家でも現況と登記地目とで判断を見誤ってしまうポイントなので注意してみてください(^^)/。
現況が農地の状態で、将来の宅地転用に向けた対策を立案する場合には?
生産緑地など、将来の宅地転用を見越して家族信託を行いたいニーズに対しては、現時点が農地である以上は、信託契約はできません。宅地転用と同時に信託をすすめるか、農業委員会の転用許可等を得ることを停止条件に信託契約を行い、転用時に信託契約の効果を発生させるという対応をせざるを得ないのが現状です。
許可等を得られた時点で、信託登記手続きを行うことができるのですが、その際の登記申請手続きを農地所有者本人ができる判断能力があるのかという問題もあります。
そのため、認知症対策として信託を検討するのであれば、宅地転用と同時に進めるしかないと考えられます。
転用時に融資を受ける場合も、融資の際に委託者の連帯保証を求めるなどの対応もでてくるので、やはり信託と転用(融資を活用する場合は融資も)は、同時期で進める必要が実務的にでてきてしまいます。
信託を活用した融資の考え方については、別の記事で詳しく解説していますので、そちらを参照してみてください。
農地を宅地に転用し、家族信託・民事信託するための方法
農地を宅地に転用するためには農業委員会の許可又は届出を得る必要があります。
その方法は、農地法第4条と第5条の転用です。
農地法第4条転用
農地所有者自らが転用する場合に活用します。
具体的には、信託契約前に農地の所有者本人(財産管理を託す“委託者”)が宅地に転用します。
農地法第5条転用
農地を農地以外に転用する目的で行う権利移動がある場合に活用します。
具体的には、先に信託契約に伴い受託者に農地の所有権を移動させ、その後に受託者が宅地に転用します。
農地法第4条転用の場合には、農業委員会の許可等を得た後、農地所有者である親本人が農地から宅地への転用と建物建築を行います。農地から宅地への地目変更登記のタイミングは建物完成時となるため、建物完成後に初めて信託契約を行い、受託者に財産管理を任せる形になります。そのため、建物完成時迄は親本人の判断能力が求められることになるため、現時点から認知症対策としては活用できません。
農地法5条転用の場合には、農業委員会の許可等を得た後、信託契約を行い、受託者に農地の所有権が移転させます。そのため、農地転用、そして建物建築を行っていくのは受託者ができるので、認知症対策として家族信託を活用する場合には、農地法第5条転用の方法を採用すべきです。
その他、農地と信託、遺言の検討すべきポイントのほか、生産緑地で注意すべきポイントを下記の記事でも詳しく解説していますので、興味ある方は是非ご覧ください。
まとめ
- 農地のまま信託できない
- 現況が宅地であれば、登記地目が農地でも信託できる
- 農地を信託財産とするには、前提として農地から宅地への転用していく必要がある
- 転用を行う場合には、農地法4条と5条の転用の違いを理解しておく
- 認知症対策として信託を活用する場合には5条の転用ですすめるべき
将来、相続対策で生産緑地を活用処分できるように家族信託・民事信託で対策をしたいという相談に対しては、現時点で農地である以上は、信託をすることが難しいと回答をせざるを得ないのが現状です。
そのため、宅地転用予定の農地については、現時点では条件付信託契約を締結する、又は、信託はせずに、任意後見制度で対応するなど他の仕組みを検討する必要があります。
どのような仕組みがベストか専門家の腕が問われます。
状況に応じた提案ができるように、勉強しておく必要がありますね。
家族信託契約書を作成する際にどのように設計・起案していますか?
家族信託というのは、士業・専門家にとって遺言や成年後見では対応できなかった範囲をカバーできる「一手法」です。自由度が高い分、お客様のニーズにあわせた対策を設計できます。しかし、一方で、オーダーメイドの契約書というのは経験も必要。そして、制度の歴史も浅く十分な判例もない状況も重なって、なかなかハードルが高く感じる方もいらっしゃるでしょう。
特に、家族信託契約書作成になると士業・専門家の技術が問われます。
もし、間違った信託契約書を作成してしまうと、本来支払う必要がない税金が課税されてしまう、金銭を管理する信託口口座が開設できない、一つの条項がないだけで不動産の売却処分等ができないといったリスクが発生してしまいます。
ここができるのとできないのとでは、士業・専門家にとっては大きな差でもあります。
今回、家族信託組成数400件を超える信託サポート件数TOPクラスのリーガルエステートがその信託契約書の最新情報とともに、作成手法について解説します。
こんな方にオススメです
・これから家族信託をやっていきたいと思っている方
・家族信託契約書を起案する方
・顧問先や顧客に家族信託を提案し、他の士業につなぐ方
セミナーでは、家族信託契約の内容と法務、税務の中でも特に重要なことをダイジェストでお伝えします。
【士業・専門家のためのゼロから始める家族信託契約書解説セミナー】
今回のセミナーでは、主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。
- 間違った信託契約書を作成した場合の3つのリスク
- 無駄な税金を払わず、預金口座凍結を防ぐための家族信託契約スキームの徹底解説
- 契約書で要注意!自益信託と他益信託。契約時に想定外の税金がかかることも!?
- 不動産所得がある顧客には要注意!知っておきたい損益通算禁止のリスクと回避方法
- 信託契約後の金銭を管理するための信託口口座の開設手続きの流れ
- 不動産が売却できない!を防ぐための信託契約条項と登記の方法は、ズバリこれ
- 委託者の想いを叶える財産の引き継ぎ方と契約書の定め方とは?
- 信託終了時に想定外の税金が!?信託契約で絶対もれてはいけない契約条項
- 適切な資産承継を考えるためには出口戦略(終わり方)が重要
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]